山を見る・山と語る 11
南九州に金脈を探す―アマチュアの初夢―
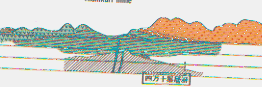 |
| 第1図 菱刈鉱山地質断面図 金属鉱業事業団(1990) |
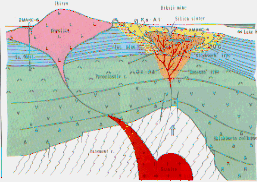 |
| 第2図 引治鉱山地質断面図 金属鉱業事業団(1991)を一部改変 |
一昨年“ゴールドシンポジウム'91イン九州”で見た引治の断面図がこびりついている(第2図)。酔眼で見ると菱刈そっくり(第1図)。ただし、九州中部地区は別府―島原地溝の中にあり、北薩地区は鹿児島地溝の外にある。そこでいささか性急だが陥没は本質的でないとして除外しよう。もちろん、陥没構造の存在そのものを否定している訳ではないが、陥没説が定説なようなので、敢えて天の邪鬼をやってみる。 この30年、日本の地質学界では陥没説が一世を風靡し、索強付会、日本中至るところ陥没盆地が想定された。いわば日本列島穴ボコだらけのアバタ面という訳である。恐らく構造運動の基本はベロウソフ流の垂直昇降によるのだとの信条が根底にあるのだろう。そろそろもうこの辺で陥没の呪縛から解き放たれてもよい時ではなかろうか。なお、陥没構造の周縁部に金鉱床が胚胎していると説く人もいるが、周縁しか基盤が露出していないからであって、陥没のど真ん中にも割れ目はあるだろうから、そこに鉱床があってもおかしくはない。
閑話休題、私は元褶曲屋、アバタ面よりも曲線美のほうが好きだ。その目で見ると、引治も菱刈も背斜構造ではないか。菱刈の場合、鉱脈は背斜軸部に平行である。褶曲に伴って軸部にできた引張割れ目に鉱床が胚胎したものであろう。そう言えば、学生時代、背斜に伴うsaddle reef型鉱床の断面図(オーストラリアBebdigo金山)を見たことがある。褶曲に伴う金鉱床の実例があるではないか。気をよくして菱刈に関わる構造的な事項を列挙してみた。
1.菱刈鉱床の構造
菱刈鉱床は、北東―南西に伸びる基盤の高まりに位置している。重力探査によれば、菱刈付近には高重力異常即貫入岩体の存在と言われていたが、四万十層群など基盤の高まりであってもよいはずである。ただし、その高まりをなす四万十層群自体の構造は、海底地すべりの影響で大変複雑であり、今のところ不明である。しかし、四万十層群と上位の安山岩類との不整合面は明らかに背斜構造をなしている。また、高まりの伸びの方向に平行な正断層により地塁状ないし傾動地塊状の形態を示すが、恐らく背斜構造形成の最末期に形成されたものであろう。
鉱脈は、この背斜軸部に存在し、軸方向に平行で、かつ、鉛直に近く、四万十層群・安山岩類の両者を切る。形成時期は約100万年前というから、前述の構造形成最末期か後褶曲期の全般的隆起運動に伴う引っ張り応力下で開口したものであろう。このように割れ目の形成、少なくともその開口は極めて新しく、鉱床成因を論ずるには、古い地質構造との関連などよりも、造地形運動や最近の地震・火山活動といった最新期テクトニクスを考慮に入れなければならないことを示している。
2.北薩地域の構造
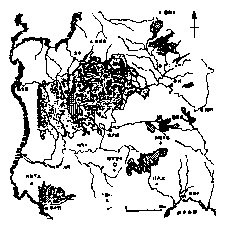 |
| 第3図 北薩地域の鉱脈群 久保田(1986)を一部改変 |
重力異常は現在の地形とほぼ調和的で、盆地で低く、山地で高い。したがって、高重力異常帯は、山地の配列と同じく北東―南西方向に伸びる。
南九州の最新期テクトニクス
周知のように日向灘付近の琉球トラフでフィリッピン海プレートが西北西ないし北西に沈み込んでいる。しかし、もっと細かく現在の地震の震源位置を見ると、プレートは一枚板ではなく、加久藤―高崎構造線と串木野―鹿屋構造線(いわゆる鹿児島中央構造線)付近で分断されており、それぞれブロックごとに厚さも沈み込みの傾斜も異なる(長宗, 1988)。両者は九州―パラオ海嶺のちょうど陸上延長部に位置しているから、同海嶺の突っ込みによって形成されたと考える人も多い。
なお、上記の構造線は北西―南東の走向を持ち左ずれと説明されているが、地表地質で確認されている訳ではなく、ましてプレートの裂け目の地表における現れだと証明されている訳でもない。単にブロック境界の位置がその付近に当たるというに過ぎない。これらと関連した北西―南東方向の左横ずれ断層(トカラ海峡や宮古凹地など)が南九州から琉球列島にかけて数多く存在する。
また、九州山地は第四紀に入ってから急速な隆起をしており、その量は最高1,000mにも達する(第四紀地殻変動グループ, 1955)。
4.金鉱脈群の形成機構(憶説)
以上の事実から、鉱脈群の形成機構を憶測逞しく推定してみる。南東からのプレートの押しによってそれにほぼ直交する北東―南西方向の割れ目が形成された。あるいは、上記のプレートの裂け目に伴う左横ずれ断層によって北東―南西方向の割れ目がRiedel shearとして形成されたのかも知れない。ただし、これでは基盤の高まりは説明できない。やはり、褶曲説のほうがよさそうだ。そうなると、褶曲軸に直交する胴切り節理に鉱脈があってもしかるべきだが、例えば錫山などがその例として挙げられるだろう。金鉱脈についてもこの方向を探してみる価値はありそうだ。
いずれにせよ、こうしてできた割れ目が100万年以降の急速な隆起に伴って開口した。そこに鉱液が進入し、開口に伴う減圧によって沸騰して金を沈殿させたのであろう(『ぼなんざ』1991年4月号参照)。
もちろん、いくら割れ目があっても、火山活動がなければ鉱液は存在しないから、火山フロントよりも内側でなければ困る。
5.金鉱脈のありそうなところ
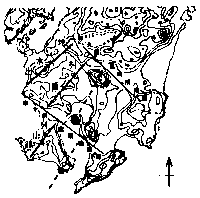 |
| 第4図 薩摩半島の曲隆地形 第四紀地殻変動グループ(1955)の接峰面図に加筆 |
そうなると、地下に伏在した基盤の曲隆部ということになる。鹿児島は温泉県だから結構ボーリングはあるが、四万十層群まで達したボーリングがあるのは、出水山地など付近に四万十が露出したところの周辺地域が大部分である。広域の地震探査をやって欲しいものだ。やむなく別の推定方法を考えてみる。
前述のような基盤の波曲(以下基盤褶曲という)があるとすると、どのくらいの波長なのだろうか。先ほど造地形運動と述べたことに触発されて地形を偏見で見てみる(第4図)。北東―南西方向の高まりはないだろうか。あるある。先ず出水山地が北東―南西に伸びている。ここでは四万十層群が露出し、14Maの紫尾山花崗岩類が貫入している。縁辺部には川内・紫尾・宮之城などの温泉が並ぶ。大口鉱山はこの延長に位置する。次いで、宮之城盆地を挟んで、約20kmほど離れて薩摩郡の南東境界をなす山地(仮に八重山列と呼ぶ)が北東―南西方向へ伸びている。四万十層群は露出していないが、火山岩類が高所に分布している。菱刈・山ヶ野などの鉱山や湯之尾・藺牟田池・市比野・湯之元などの温泉群がある。さらに約20km南東へ行くと、霧島~桜島の活火山列、すなわち火山フロントになる。つまり、基盤褶曲の褶曲波面は南東に緩く傾斜しており、南東に行くほど基盤の四万十層群は深くなっていて、火山活動は若くなる(第5図)。当然、鉱脈の年代も南東側ほど新しくなるであろう。もしもこの基盤褶曲が複褶曲だとすると、これより短波長の背斜が地下に伏在していてもよい。串木野はそのような二次オーダーの背斜に当たるかも知れない。
串木野―鹿屋構造線より南側はどうであろうか。あまりはっきりしないが、鹿児島市錫山から金峰山を経て坊津町へ続く山なみ(仮に錫山列と呼ぶ)がある。ここには四万十層群が露出しているが、前述の八重山列の延長かも知れない。これには錫山・樋渡・鹿篭・春日・岩戸などの鉱山がある。構造線の北側と同様、約20kmほど南東に池田湖~開聞岳~トカラ列島の火山列がある。ここには大谷鉱山などがある。
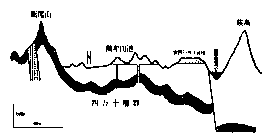 |
| 第5図 北薩の基盤構造(憶説) 北東―南西方向の推定地質断面図 |
まとめてみる。南東からのプレートの圧縮により、北東―南西の軸を持つ波長約20kmの基盤褶曲が形成された。褶曲波面は南東側に緩く傾斜し、軸は恐らく北東にプランジしている。その背斜構造に伴う引っ張り割れ目に火山岩が貫入したり鉱脈が貫入した。火山活動は火山フロントに近づくほど年代が若い。こんな風に考えられないだろうか。
酔った頭でこんなことを考えた。黄金郷鹿児島の夢、黄金の国ジパング再来の夢である。恐らく専門家は一笑にふすだろうが、アマチュアの夢も捨てたものではない。瀬木耿太郎氏は著書『石油を支配する者』(岩波新書)で「いつの世でも、専門家たちの頑迷固陋さを乗り越えていくのは、既成観念にとらわれないアマチュアの精神である」と述べ、サウジアラビアの石油開発をめぐるエピソードを紹介している。バハレーンの利権が売りに出された時、石油地質学者であったアングロ・ペルシア(現British Petroleum Co.)のカドマン社長はアラビア半島に石油など存在するはずがないと固く信じていたので取り合わなかった。当時石油は地表に油徴があるところにしか発見されていなかったし、既に背斜軸部に石油が胚胎することも知られていたが、砂漠では地表で地質構造を把握することは不可能だったからである。結局、アメリカのソーカル(現Shevron Corp.)が入手し、イギリスは後れを取った。以後中東世界にアメリカが強大な影響力を奮う基礎が築かれたのである。
どうだろう、一つジャンボ宝くじだと思って、シラス地帯のど真ん中にでも深いボーリングをしていただけないだろうか。ボーリングと言えば、少なくとも温泉や建設関係のボーリングデータは鉱山地質の目でもう一度全部見直す必要があると思う。金属鉱業事業団がボーリングをやっている引治は猪牟田カルデラの縁辺部に当たるが、猪牟田ダム建設のために建設省は10年以上前から30億円に上る巨費を投じて地質調査を行っている。ボーリング総延長約12,000m、横坑約2,000mもある。いくら役所の縄張り意識とはいっても、こうしたデータを利用させてもらわない手はない。鉱脈やシンターは単なる石英脈とされ、変質帯は粘土化した軟弱帯と記載されているだけだろう。コアはまだ保存されているし、横坑はまだ入って観察できる。仮に鉱徴はなくても、猪牟田カルデラの成因を論ずるのには、大いに役立つに違いない。
基盤褶曲などを持ち出して槙山次郎先生の時代に引き戻すのかと叱られそうだし、だんだん支離滅裂、話がそれてきたからこれで筆をおく。
(『ぼなんざ』, №206, 1993 掲載)
ページ先頭|地質屋のひとりごともくじへ戻る
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1997年8月19日