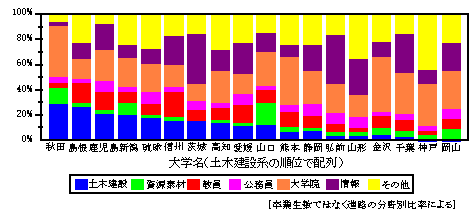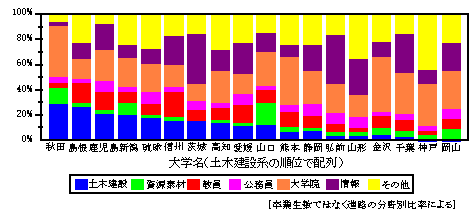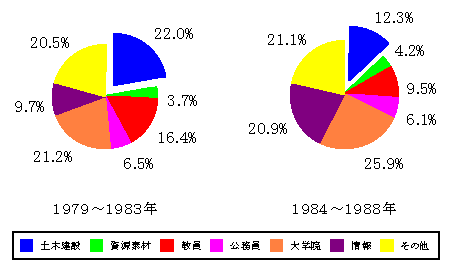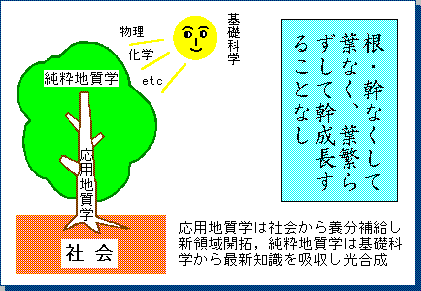岩松 暉(『応用地質』32巻4号,184-187,1991)
(初出:日本応用地質学会九州支部会報 No.11,1990)
1.地学系学科卒業生の進路
最近は大変景気がよい。毎年求人に訪れる人だけで100人に及ぶ。まさに嫁1人に婿8人である。青田刈りどころか,苗のうちから確保しようと奨学金まで出す会社もある。ところが肝心の学生はなかなか就職したがらない。世に言うモラトリアムである。しかもその就職先が問題,地学科を出たのに地質関係の会社に行く人はごく僅かで,私の勤務する鹿児島大学で2割強でしかない。これでは大変と,国立19大学地学系教室主任会議に提案して実態調査を行っていただいた。結果を見て唖然とした。わが大学はよいほうなのである。最近5年間の平均で土木建設・資源素材といった地質関係の会社に就職する率が2割を超えているのは秋田・山口・新潟・島根・鹿児島・琉球の6大学に過ぎない(図-1:富山大学は回答なし)。わが応用地質学会および業界に直接かかわる土木建設系に就職する人が2割を超すのは秋田・島根・鹿児島・新潟の4大学だけである。全体では約1割で,その前の5年間が約2割だから半減である(図-2)。これに反比例してコンピュータソフト会社へ就職する人が倍増している。ソフト会社は地質関係のソフトも作る場合があり,専門家としてシステムの構築に当たるのだから専門を生かせる職場なのですと美辞麗句を並べるが,実際は数を充当するのに使われる使い捨てのコマなのであろう。学生も専門を生かすためにソフト会社を選んでいるわけではない。
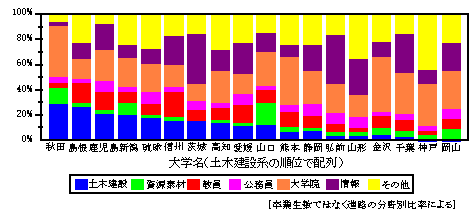 図-1 国立18大学地学系学科卒業生の進路(1984~1988年度)[国立19大学地学教室主任会議資料より作成]
図-1 国立18大学地学系学科卒業生の進路(1984~1988年度)[国立19大学地学教室主任会議資料より作成]
行政管理庁が1989年に秋田大学の監査を行った際,卒業生名簿からランダムに特定個人を抜き出して,専門と無関係な職場に就職した理由を詰問した由,そんな学科は税金のムダ遣いだから縮小廃止せよと言いたいのであろう。お役人的な短絡思考ではあるが,こうした面からも地学科が外圧に曝されることは必至である。
こうなった理由はいろいろ考えられるが,大学と産業界双方に問題があるように思う。
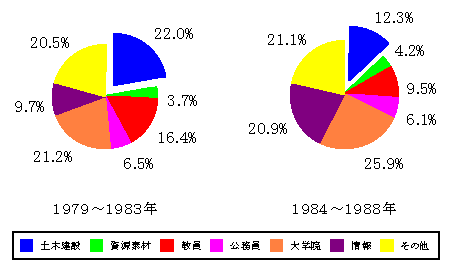 図-2 国立18大学地学系卒業生の就職先の変遷(1979~1988年度)
図-2 国立18大学地学系卒業生の就職先の変遷(1979~1988年度)
2.教える側の問題点
大変ショッキングな話を聞いた。先日ある地質コンサルの若い地質屋さんとフィールドを一緒に歩いたときのことである。話が前述のような就職のことに及んだ。「私の世代はそれほどでもなくクラスの半数は地質コンサルに行きましたが,問題がないわけではありません」と,こんな話をしてくれた。
「地質コンサルに行ったクラスメート10数人のうち,今でも地質をやっているのはその半数に過ぎません。あとの人は完全に地質とは無関係な仕事をしています。彼等は学生時代,岩石鑑定などはうまかったし,地質が好きでフィールドはよく歩いてすばらしい地質図を描きました。総じて自分などより数等上でした。しかし,コンサルに入ってみると,あまりに土木的で彼等のイメージにある地質学とは相当隔たっていますから,こんなはずじゃなかったと会社を辞めてしまうのです。生活の糧は別な手段で稼いで,地質は趣味にとっておくのだそうです。」
確かにハングリーでなくなったから,何をやってもメシは食える。好きでも嫌いでも社会に自分を適合させていくしか生きる道のなかった時代とは違う。しかし,それだけと考えるよりもっと深刻な問題を投げかけている。すなわち,大学における地質学教育の反省をせまっていると考えるべきではないだろうか。地質をやめて行った人たちは学生時代優等生だったのである。彼等が大学で教わった地質学と実社会で日々活躍している地質学とは全く異質だったから,拒絶反応が出たのだ。彼等の指導教官の名前を聞いて,何となくうなずけた。要するに象牙の搭のアカデミズムそのものである。こういう先生に教わった学生が彼等なりに受け止めた地質学は,少し擬画化して言うと,ロマンに満ちた太古の昔の夢物語か,収集癖の好事家が化石を集めて喜んでいる麗しい趣味の世界だったのであろう。土木地質学など地質学ではないのだ。科学の名に値しないと考えているに違いない。中には「役に立たないことをやっているのを誇りにしているのが理学部だ」などと公言している先生もいる。こうした応用科学に対する無知・偏見は今に始ったことではない。地質工学の創始者渡邊 貫(1952)は純正科学と応用科学について,次のように述べ悲憤慷慨している。
『人工雪の研究で有名な北大教授中谷宇吉郎博士が嘗つて筆者に次のような憤懣を漏したことがあった。“大学や研究所で実用方面への応用に力をつくすと学者が恰かも堕落したようにいう人がある,実用目的があってこそ始めて学問の研究に拍車がかけられるのであって,単なる象牙の搭での孤独な存在は人生に於て無意義である”と。
筆者もこの点同感であって嘗つて有島武郎が云ったように,“夫れが単なるカード・ボックスの整理にすぎないような仕事でも,そのことが偶々大学構内の片隅で行はれているということだけで,夫れを学問と云ったり学者としたりすることは間違っている,学問とは学者とは何等かの方法によって人生に光明を与えるものでなければならぬ”。
Academic foolという言葉があるが,我が国の大学人種の中に往々にしてこの種の人間がをり,理科系の学者が実用方面に赴くのを恰も学問の堕落の如く考えている愚者がいる。』
こうしたAcademic foolは,何もお年寄りのクラシックな学者先生に見られるだけではない。ここ20年来,地質学と社会の接点であった資源産業が衰退して地質学が実社会から切り離されたところへ,プレートテクトニクスのようなフィールドでなかなか検証しにくい学説が導入され,思弁的な学風が支配的になってきた。その上,博士失業などが深刻となり,自ら視野を狭めて狭い領域の専門家として早く名を成す必要に迫られたため,タコツボ型の若手研究者が大量に養成されている。このような人たちが教育に当る時代になったのだから,“カッコいい学問にあこがれる”学生が育つのは当然である。
こうした応用科学軽視の風潮と同時に,純粋地質学自体が活気を失い若者にとって魅力が薄れているのも,いま一つやる気を起こせない原因になっていると思う。世間一般では地球科学≒地球物理学と考えられており,地質学の影は薄い。プレートテクトニクスの壮大な仮説にしても,地球物理学が生み出してきたものであり,地質学の本質的な貢献は少ない。1989年春に測地学審議会が「地球科学の推進について」と題する建議を行った。当然のことながら地球物理学を柱とするビッグプロジェクトが推進課題とされている。地質学は添え物扱いである。今後この建議に沿った学科改組の嵐が大学に吹き荒れるに違いない。しかし,地球物理学のほうが何時も地質学をリードしていた訳ではない。戦前,資源産業が華やかだった頃は,地質学のほうがはるかに革新の息吹に満ち活気があったが,一方地球物理学は寺田寅彦の随筆に見られるように高踏的サロン的であった。やはり,近年地震予知計画など地球物理学が社会のニーズに積極的に応える姿勢に立ったとき,急速に発展してきたと言える。これに反し,地質学は実社会から遊離し,趣味的博物学的方向に,いわば先祖返りしている。純粋科学と応用科学は車の両輪であり,両々相俟って発展するのである。地質学を1本の樹に例えれば,社会という大地にしっかりと根を下ろし,養分を吸収している太い幹が応用地質学であり,その上に緑豊かに繁っている葉が純粋地質学である(図-3)。根や幹がなければ葉は存在し得ないし,葉が繁り日光(物理・化学などの関連諸科学)の恵みを得て大いに光合成を行わなければ,幹も大きくなれないのである。今の日本の地質学は,根が貧弱で萎れている樹に例えられよう。
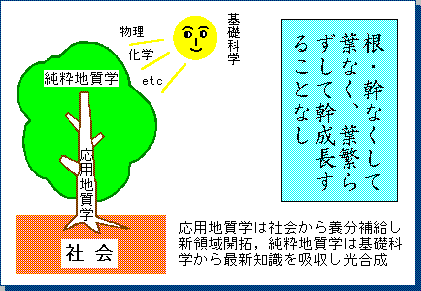 図-3 応用地質学と純粋地質学
図-3 応用地質学と純粋地質学
もう一つ,地質の好きな学生が土木地質に違和感を持つ理由に,数字に還元して考える発想が身についていないこともあるように思う。もともと地学科に進学してくる学生は,数学・物理が弱い(鹿児島県の場合,高校では理系クラスは物理・化学必修で,地学は文系しか選択できない由)。しかもフィールドの好きな(フィールドしかできない?)層序学関係の学生ほど極端に弱い。しかし現場では,c・φだ,切土勾配だと数字がたくさん出てくる。どうもそれでアレルギーを起こしているらしい。こうした地質屋的地質屋が書いた報告書は,岩石の顕微鏡写真まで付いて地質の記載はやたら詳しいが,設計施工に必要不可欠な肝心のデータがないと,建設コンサルやゼネコンからは不評を買う。当然上役からは叱られる。当人は大学なら誉められるようなすばらしいレポートを書いたのにと不満が鬱積する。それで辞める人もいるらしいのである。確かに地質学は総合科学ではあるが,大きく見ればやはりphysical scienceの中の一分科であることが忘れられている。もっと数理的な教育を強化しなければならない。
3.学ぶ側の問題点
学生気質の変化も著しい。まず何よりも地学科に入学してくる者には不本意入学者が多い。昔は山や自然が好きだといったそれなりの志望理由があったが,共通一次試験発足以来,入りたい大学より入れる大学,コンピュータが偏差値で選んでくれた第一志望なのである。したがって,かつては山岳部やワンゲル・ラグビー部など身体を動かす運動部系サークルに入る学生が多かったが,今は極端に少ない。それも基礎体力づくりのためにハードトレーニングを強制される“部”よりも,ゲームを楽しむ“同好会”やガールハントの“愛好会”が花盛りである。また,受験競争の激化に伴い,幼時から塾だ家庭教師だと勉強しないと国立大学に入れなくなったから,都会の進学校出身者がほとんどで,郡部出身は稀になってしまった。自然の中でどろんこになって遊んだ経験がないのである。したがって,山を歩く楽しみどころか,フィールド調査などは苦役以外の何物でもない。
もちろん,社会の変化が学生気質に深く反映しているのは当然である。戦後の混乱期以来,食える生活,よりよい生活を夢見てともかく遮二無二働いてきた。今日の日本の繁栄はこうした“仕事人間”“モーレツ社員”が築いてきたのである。しかし,高度成長から一転して低成長,出世も先が見えている。しかも狂乱地価で一生働いても家一軒買えない。「どうせ努力しても所詮…」と極めて冷めており,“無気力症候群”などという言葉が流行って久しい。それにほとんどが一人っ子かせいぜい2人,両親の溺愛と期待を一身に集め,地球は自分を中心に回転してきたから,幼児性・自己中心性の抜けきらないまま大人になってしまった。当然,他者に対する思いやりはなく,額に汗することを厭う。また,管理主義教育の徹底で何事も受け身,命令しなければやらないし,命令したことしかやらない。しかも飽食の時代で,かつ,求人難の時代,遊んでいても適当にメシは食える。レジャー資金さえ手に入れば,フリーアルバイターのほうが気楽でよい。土木建設は,キツイ・キタナイ・キケンの3Kと言われて敬遠されるのは当然である。
4.受け入れる側の問題点
学生を受け入れる業界のほうにも問題がある。地質コンサルタントに就職した若い先輩が母校に遊びに来たとき,後輩たちに胸を張って誇らしげに仕事を語る人は皆無に近い。曰く,
出張が年間100日を越す。赤ん坊に顔を忘れられ,人見知りされて泣き出されてしまった。
毎日のように10時11時まで残業で,しかも残業手当がまともに出ず大部分ただ働き。日曜出勤もしばしば,過労死もひと事ではない。週休2日は夢のまた夢。
労使関係が前近代的で,家族的と言えば聞こえがよいが,要するに封建的なしがらみで一方的に奉仕させられる。
他の職種に就職した同級生より月給が確実に1万円は低い。使っているアルバイターのほうが手取りがよい。
同じ安いのなら公務員みたいに威張りたい。日本はかつての東欧以上に官僚国家,生殺与奪の権を握っているから,お役人の前ではペコペコしなければならない。実力があるならまだしも素人のくせに威張る奴がいる。
神様,仏様,お施主様,いつもゼネコンの顔色をうか
がわなければならない。
いくつもの現場を掛け持ちさせられ,良心的な仕事ができない。勉強して技術を向上させる暇もない。
などなど……,愚痴が口を突いて次から次へと出てくる。まさに3Kそのものか,それ以上。当然,後輩たちはその会社には絶対に行かない。それだけでなく,地質調査業そのものを敬遠する。
ぜひ若手が意気揚々として後輩たちに語ることのできる,魅力ある業界にしてもらいたい。いつも転職のことが念頭にあるようでは困る。“兎小屋に住む働き蜂”の時代は確実に過ぎ去っている。良きにつけ悪しきにつけ,新人類が社会に進出する時代になったのである。彼らの「人間らしいゆとりのある生活がしたい」という要求に応えることは国際批判に応えることでもある。仕事=生きがい論だけでは済まない。同時に,新人類の持つ積極面を正当に評価し,それを取り入れる姿勢と施策が求められていると言えよう。一考を促したい。
根本的には地質屋の社会的地位の向上をはかることが第一である。欧米ではgeologistの社会的地位は大変高いという。わが国では,同じコンサルタントなのに,弁護士は社会的に尊敬され名士扱いされるが,普通はコンサルティングそのものに対する評価が低い。富士通の図書館管理システム1円受注事件がそれを象徴している。役所やゼネコンの仕様書通りに調査するだけでなく,欧米のgeologistのように土木工事全体に発言権を持つ重みのある存在になりたいものである。土木屋から一目置かれるような真に“使える応用地質学”を創造していくことが基本だが,お役所の積算システムなども改善する必要があろう。1989年建設コンサルタント中長期ビジョンが出された。ATI構想と銘打たれ,「魅力に満ち(Attractive),技術を競う(Technologically spirited),独立した(Independent)知的産業を目指して」いる。この構想の早期実現を切望する。
5.おわりに
問題点と題したので,かなり否定的な側面を強調し過ぎたきらいがある。例えば新人類にしても,われわれの世代にない優れた感性を持っており,興味を抱いたことには結構頑張る。自己中心的と述べたが,ボランティア活動などを一生懸命やる者もいるのである。
現状を単に嘆いているだけでなく,21世紀の飛躍を実現し得る土台を,この残された10年のうちに築いていかなければならない。幸いこの応用地質学会は産・官・学の3者が対等に参加している場である。大いに協力の実を挙げ,この課題をやりとげたいものである。
引用文献
渡邊 貫(1952):地質工學の現在及び將來. 地質工學,1輯,1-4.
ページ先頭|応用地質雑文集もくじへ戻る
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:1997年8月19日