岩松 暉(地質学会関東支部シンポ「地質学の現状と課題(その1)―各界からの問題提起―」, 1-12, 1993)
1.今大学で何が進行しているか
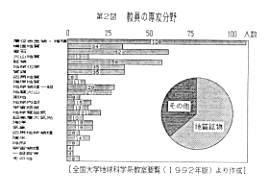
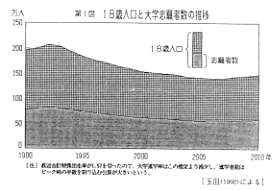 大学は今激動期にある。戦後の新制大学発足時に匹敵するという。ただベクトルは全く逆,「少子時代」を迎えて縮小整理の方向にある(第1図)。農学部・工学部の改組は大方終わり,教養部解体に伴って理学部が俎上に上っている。その上地球科学系では,89年の測地審建議・90年の国立10大学理学部長会議提言の方向に沿って地球惑星科学への転換がはかられている(第2図)。
大学は今激動期にある。戦後の新制大学発足時に匹敵するという。ただベクトルは全く逆,「少子時代」を迎えて縮小整理の方向にある(第1図)。農学部・工学部の改組は大方終わり,教養部解体に伴って理学部が俎上に上っている。その上地球科学系では,89年の測地審建議・90年の国立10大学理学部長会議提言の方向に沿って地球惑星科学への転換がはかられている(第2図)。
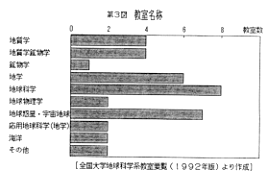 既に10大学(旧制帝大+筑波大・東工大・広島大)のうち,地質学・鉱物学の名の付く教室があるのは北大・東大・京大の3大学になってしまった(第3図)。北大・京大の地鉱教室は地球物理と合体して地球惑星科学教室への改組を検討中というから,全滅は間近い。
既に10大学(旧制帝大+筑波大・東工大・広島大)のうち,地質学・鉱物学の名の付く教室があるのは北大・東大・京大の3大学になってしまった(第3図)。北大・京大の地鉱教室は地球物理と合体して地球惑星科学教室への改組を検討中というから,全滅は間近い。
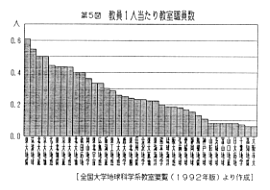
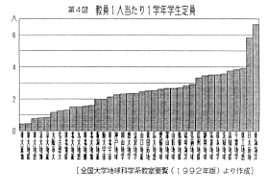 一方,欧米からの基礎研究ただ乗り論に応えると共に,国際競争に打ち勝つ技術革新を遂行できる人材を養成するため,大学院重点化構想が急ピッチで進行している。旧制大学を大幅に拡充して大学院大学にしようとするものである。新制と旧制では今までにもさまざまな格差が存在していたが(第4図・第5図),こうした大学にさらに先端科学研究費や施設整備費の重点投資が行われる。また,従来1講座当たり2名の大学院学生定員を一挙に5名に増やすことになっており,東大から順次実施に移されつつある。この結果,いわゆる玉突き現象が起きて中央への人材の一極集中が加速されている。旧制大学の間ですら院生の奪い合いが生じているのだから,前述の少子時代を勘案すると,新制大学大学院など不要に近い。
一方,欧米からの基礎研究ただ乗り論に応えると共に,国際競争に打ち勝つ技術革新を遂行できる人材を養成するため,大学院重点化構想が急ピッチで進行している。旧制大学を大幅に拡充して大学院大学にしようとするものである。新制と旧制では今までにもさまざまな格差が存在していたが(第4図・第5図),こうした大学にさらに先端科学研究費や施設整備費の重点投資が行われる。また,従来1講座当たり2名の大学院学生定員を一挙に5名に増やすことになっており,東大から順次実施に移されつつある。この結果,いわゆる玉突き現象が起きて中央への人材の一極集中が加速されている。旧制大学の間ですら院生の奪い合いが生じているのだから,前述の少子時代を勘案すると,新制大学大学院など不要に近い。
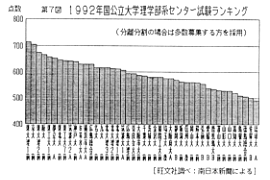
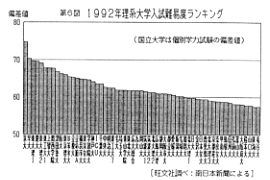 その上,受験生の文系志向・国立離れの問題がある。1990年のデータでは大学志願者の2割しか理系を希望しないという。理系は受験科目が多い上に,大学ではハードな実験や卒論がある。社会に出てからそれが報いられるのならまだしも,法経出身の経営者にアゴで使われる。これでは優秀な人材が理系に進学するはずがない。重厚長大型産業が国を興し生活を豊かにすると考えられてきた高度成長期以前の時代には,それでも理系進学者が多かった。経済のソフト化・三次産業化に伴って,若者の価値観が変るのは当然であろう。理系偏重の国立が敬遠される根源もそこにある。低廉な国立授業料というメリットが失われた今,受験生を引きつけるのは難しい。今や早慶は言うに及ばず,日東駒専なる言葉もできたように私学の優位は歴然としている。若者の都会指向と重なり,地方に存在する国立大学(いわゆる地方大学ではなく北大・九大も含む)が私学や都会の大学に優秀な人材を奪われ,激しい地盤沈下に見舞われている。第6図・第7図のようなものが堂々と新聞に発表されるから,ますますこの傾向が助長される。嗚呼。私が勤める鹿大地学科で,入学から卒業までの追跡調査を行なったことがある。以前は入試成績は必ずしもよくないが卒業時にはなかなか優秀な学生がいた。ところが,数年前から入試成績と学部での学習意欲に高い相関を示す傾向が出てきた。つまり,下位成績といっても昔と今とではレベルが違って,最近は基礎学力がないために,知的好奇心すらわかないような深刻な状態なのである。しかも地球科学に興味を持っているならまだしも,コンピュータが選んでくれた第一志望で,不本意入学者がかなりの比重を占める。元々文系志望だった者までいる始末である。その上,解法を丸暗記するのが学問だとの発想が染み付いているから,「科学する喜び」とか「自然界の不思議に感動する」といったことは全然ピンと来ないらしい。先生はいつも正解を知っていて,自分たちは練習問題を与えられているだけと信じている。したがって,何事も受け身で指示待ち人間である。卒論のように敷かれたレールのない場合には,どちらに向かって走ってよいか分らず呆然とするしかない。登校拒否など自我を持っている証拠で,まだ救いようがあるのかも知れない。一番困るのは「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則が働くことである。「赤信号みんなで渡れば恐くない」を実践するため,能力のある者までダメになってしまうのである。「こうした学生を目覚めさせるのが教員の力量というものだ」といったきれいごとを言える段階ではなくなった。要するに総じて現在の大学は,大学という名のレジャーランドに成り下がり,学問の府なる言葉が死語になって久しい。
その上,受験生の文系志向・国立離れの問題がある。1990年のデータでは大学志願者の2割しか理系を希望しないという。理系は受験科目が多い上に,大学ではハードな実験や卒論がある。社会に出てからそれが報いられるのならまだしも,法経出身の経営者にアゴで使われる。これでは優秀な人材が理系に進学するはずがない。重厚長大型産業が国を興し生活を豊かにすると考えられてきた高度成長期以前の時代には,それでも理系進学者が多かった。経済のソフト化・三次産業化に伴って,若者の価値観が変るのは当然であろう。理系偏重の国立が敬遠される根源もそこにある。低廉な国立授業料というメリットが失われた今,受験生を引きつけるのは難しい。今や早慶は言うに及ばず,日東駒専なる言葉もできたように私学の優位は歴然としている。若者の都会指向と重なり,地方に存在する国立大学(いわゆる地方大学ではなく北大・九大も含む)が私学や都会の大学に優秀な人材を奪われ,激しい地盤沈下に見舞われている。第6図・第7図のようなものが堂々と新聞に発表されるから,ますますこの傾向が助長される。嗚呼。私が勤める鹿大地学科で,入学から卒業までの追跡調査を行なったことがある。以前は入試成績は必ずしもよくないが卒業時にはなかなか優秀な学生がいた。ところが,数年前から入試成績と学部での学習意欲に高い相関を示す傾向が出てきた。つまり,下位成績といっても昔と今とではレベルが違って,最近は基礎学力がないために,知的好奇心すらわかないような深刻な状態なのである。しかも地球科学に興味を持っているならまだしも,コンピュータが選んでくれた第一志望で,不本意入学者がかなりの比重を占める。元々文系志望だった者までいる始末である。その上,解法を丸暗記するのが学問だとの発想が染み付いているから,「科学する喜び」とか「自然界の不思議に感動する」といったことは全然ピンと来ないらしい。先生はいつも正解を知っていて,自分たちは練習問題を与えられているだけと信じている。したがって,何事も受け身で指示待ち人間である。卒論のように敷かれたレールのない場合には,どちらに向かって走ってよいか分らず呆然とするしかない。登校拒否など自我を持っている証拠で,まだ救いようがあるのかも知れない。一番困るのは「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則が働くことである。「赤信号みんなで渡れば恐くない」を実践するため,能力のある者までダメになってしまうのである。「こうした学生を目覚めさせるのが教員の力量というものだ」といったきれいごとを言える段階ではなくなった。要するに総じて現在の大学は,大学という名のレジャーランドに成り下がり,学問の府なる言葉が死語になって久しい。
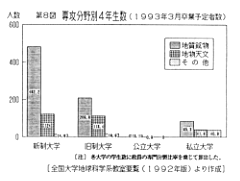 以上の問題は,わが国の地質学にとって意味するところが大きい。周知のように地質学の人材養成は主として国立大学,就中,新制大学が担ってきたからである(第8図)。第一に,大学教員の大部分を輩出している旧制10大学が地球惑星に転換することは,今後の地質学教育に重大な影響を与えることになる。恐らくフィールドサイエンスとしての地質学を教えられる人が少なくなるであろう。第二に,主として土木建設業界など実社会に人材を供給してきた新制大学のレベルダウンは,地質調査業界の技術革新にマイナスの影響を及ぼすであろう。これでは地質家の社会的地位の向上は望むべくもない。
以上の問題は,わが国の地質学にとって意味するところが大きい。周知のように地質学の人材養成は主として国立大学,就中,新制大学が担ってきたからである(第8図)。第一に,大学教員の大部分を輩出している旧制10大学が地球惑星に転換することは,今後の地質学教育に重大な影響を与えることになる。恐らくフィールドサイエンスとしての地質学を教えられる人が少なくなるであろう。第二に,主として土木建設業界など実社会に人材を供給してきた新制大学のレベルダウンは,地質調査業界の技術革新にマイナスの影響を及ぼすであろう。これでは地質家の社会的地位の向上は望むべくもない。
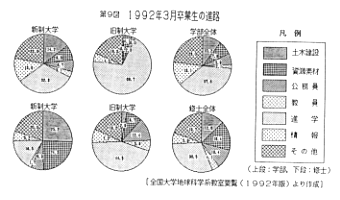 学生気質の変化も著しい。受験競争の激化に伴い,都会の進学校からしか進学できなくなったため,自然をあまり好きでない学生が増えてきた。それに少子時代,甘やかされて育ったから,額に汗して努力することを厭う者が多い。地質調査業は自然を相手にしている以上,ある程度3Kであることは避けられない。大学で学んだ専門を活かす職場に就職する者が極端に少なくなってしまった(第9図)。行管や文部省ならずとも,この行革の時代,そんな学科は潰していまえとの声が起きて当然である。恐らく大幅定員割れを起こした大学からお取り潰しの動きが出てくるであろう。レベルダウンだけでなく,実社会が必要とする人材の絶対数すら不足する深刻な事態になる恐れが強い。
学生気質の変化も著しい。受験競争の激化に伴い,都会の進学校からしか進学できなくなったため,自然をあまり好きでない学生が増えてきた。それに少子時代,甘やかされて育ったから,額に汗して努力することを厭う者が多い。地質調査業は自然を相手にしている以上,ある程度3Kであることは避けられない。大学で学んだ専門を活かす職場に就職する者が極端に少なくなってしまった(第9図)。行管や文部省ならずとも,この行革の時代,そんな学科は潰していまえとの声が起きて当然である。恐らく大幅定員割れを起こした大学からお取り潰しの動きが出てくるであろう。レベルダウンだけでなく,実社会が必要とする人材の絶対数すら不足する深刻な事態になる恐れが強い。
2.何をなすべきか
しからば何をなすべきか。何はともあれ定員確保とばかり,各大学ともこぎれいなパンフレットやポスターを作って高校に配ったり,センター入試免除の特典つき推薦入学を行ったりと,涙ぐましい努力をしているが,所詮根本的解決にならないことは明らかである。そこで,私見ではあるが処方箋を提案してみたい。与えられた標題の範囲を逸脱して,学問自体にも触れた点はご容赦いただきたい。
①魅力ある地質学の創造
もっとも基本的な点は,地質学という学問自体を活性化し,若者にとって魅力のあるものにすることであろう。若者には夢が必要である。地球惑星科学の方向もその一つであることには間違いない。地質学の研究対象が地核から宇宙まで広がることはある意味では必然である。AGI のGlossaryもgeologyを'the study of the planet Earth'と定義して,月など地球外天体を研究することの重要性について触れており,今日の事態を喝破していた。惑星の地質構造の研究にリモートセンシングの手法が応用できるといった段階から,実際に他天体物質の入手すら可能な時代になり,今や惑星が地球科学の研究対象になってきたのだ。もちろん,惑星の研究成果が初源地球の理解に大きく貢献することは論を待たない。
しかし,こうした純アカデミックな興味だけから惑星が注目されている訳ではない。第一,単なる趣味ならば1000人もの学生を養成する必要はない。今日,宇宙や惑星が脚光を浴びるようになってきたのも,通信衛星など宇宙産業がビジネスとして成立したことが大きい。宇宙空間発電や月や惑星における鉱物資源探査などが,次世代のビッグプロジェクトとして日程に上ってきたこととも関係がある。かつての産業革命期と同じように,地質学には資源とエネルギーの面での貢献が求められているのであろう。
ひるがえって,地球上のことは等閑視してもよいのであろうか。ブラジルでの地球サミットを持ち出すまでもなく,地球環境は今日の重要なキーワードの一つである。しかるに,地球温暖化のシミュレーションに気象学者の活躍が報道されることはあっても,地質学からの貢献は極めて少ない。マクロな予測の段階から,具体的な対策になった時,地質学がすぐ必要になってくる。そのための学問的準備が今の日本の地質学にあるのであろうか。産業革命を自ら遂行した欧米の地質学と異なり,明治時代に出来合いの学問いわば切り花を輸入した日本の地質学には,実用に関わることを潔しとしない象牙の搭的体質が色濃く残っている。基礎さえしっかりしていれば応用なぞ訳はない,知識の切り売りで済むと尊大に構えている学者先生があまりにも多い。
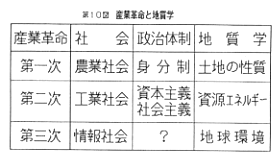 しかし,現在は学問の世界でもボーダーレス時代である。理学と工学の差が極めて接近してきた。超伝導や超LSI などナノテクノロジーはまさに物理学そのもので,基礎理論の世界でも理学が押され気味という。大型機器に頼らざるを得ないビッグサイエンスの世界のことだと軽く見るのは誤りである。社会のニーズにマッチし,社会の発展方向に沿ってそのうねりに乗った時,学問もまた発展することは科学史の教えるところである(第10図)。研究テーマにしても,社会という汲めども尽きない泉から汲み出してこそ,単なる従来の延長線上ではない斬新な発想が生まれるのだ。よく基礎研究と応用研究のバランスのとれた発展をと言われるが,IGC と日本地質学会年会の講演内容を比較すれば,日本の地質学がいかに偏っているか歴然としている。IGC におけるIUGS会長講演のような講演を日本の学会では聞いたことがない。まして大学の地質学の体系は1世紀前のままで旧態依然としている。
しかし,現在は学問の世界でもボーダーレス時代である。理学と工学の差が極めて接近してきた。超伝導や超LSI などナノテクノロジーはまさに物理学そのもので,基礎理論の世界でも理学が押され気味という。大型機器に頼らざるを得ないビッグサイエンスの世界のことだと軽く見るのは誤りである。社会のニーズにマッチし,社会の発展方向に沿ってそのうねりに乗った時,学問もまた発展することは科学史の教えるところである(第10図)。研究テーマにしても,社会という汲めども尽きない泉から汲み出してこそ,単なる従来の延長線上ではない斬新な発想が生まれるのだ。よく基礎研究と応用研究のバランスのとれた発展をと言われるが,IGC と日本地質学会年会の講演内容を比較すれば,日本の地質学がいかに偏っているか歴然としている。IGC におけるIUGS会長講演のような講演を日本の学会では聞いたことがない。まして大学の地質学の体系は1世紀前のままで旧態依然としている。
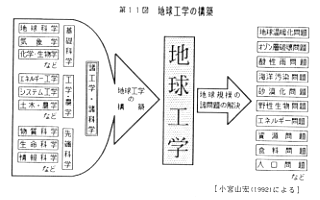 現代青年は新人類だ無気力だなどと嘲られるが,いつの時代でも青年は進取の気象に富み,意気に感ずれば目標に向かって邁進するものである。日本の地質学は若者にその目標とモティベーションを与えていない。かつて先輩たちは「山を駆け野を巡り地の幸をたずね行く,喜びを君と語らん」と誇らしげに歌っていた。石炭は黒ダイヤと呼ばれ金ヘン景気なる言葉もあった時代である。戦後復興の旗手としてもてはやされていたから,誠に意気軒昴たるものがあった。これからの時代は,自然環境と調和した持続可能な開発が求められ,物質的豊かさから真のアメニティーを追求する時代である。地球規模でも国内規模でも社会基盤の整備が求められている。すなわち,地質学はこうしたインフラテクノロジーの面で大いに貢献しなければならない。土木建設の下請としての地質調査ではなく,どこに何を何のためにどのように作るのかといったプランニングの初期の段階から地質家がタッチし,全体像に責任を負う立場に立つ必要がある。環境設計などというと神をも畏れぬ響きがあるが,地質家はアースデザイナーなのである。乱開発時代には地質調査に行くとムシロ旗で迎えられたこともあったが,土木の僕・乱開発の先兵では若者にソッポを向かれて当然である。これからは自分たちの住環境をよりよくしてくれる味方として歓迎され尊敬されるようでなければならない。そのためには従来のルーチンの地質調査に甘んじていてはダメで,土木関係者に一目置かせるような鋭利な武器を学問的に提供できる素地を今から築いていく必要がある。学際的な分野を創造していくことが急務である。変り身の早い工学方面では,環境システム工学や果ては地球工学(第11図)を唱え,次代の産業革命で主役たらんと準備おさおさ怠りない。数千万年前の古環境を論じて環境科学をやっていると称しお茶を濁すようでは,もはや地質学には未来はない。101~103年オーダーの近未来について定量的に予測し,具体的解決策を提言できる力量が必要である。「現在は過去の鍵」という時代は過ぎた。「過去は未来の鍵」と胸を張れないようではダメである。今回もバスに乗り遅れるようなら,ごく限られた理学部に博物学者を少数残しておくだけにして,工学部に地質工学科を新設するか,社会開発工学科に地質工学講座を併設するしかないであろう。
現代青年は新人類だ無気力だなどと嘲られるが,いつの時代でも青年は進取の気象に富み,意気に感ずれば目標に向かって邁進するものである。日本の地質学は若者にその目標とモティベーションを与えていない。かつて先輩たちは「山を駆け野を巡り地の幸をたずね行く,喜びを君と語らん」と誇らしげに歌っていた。石炭は黒ダイヤと呼ばれ金ヘン景気なる言葉もあった時代である。戦後復興の旗手としてもてはやされていたから,誠に意気軒昴たるものがあった。これからの時代は,自然環境と調和した持続可能な開発が求められ,物質的豊かさから真のアメニティーを追求する時代である。地球規模でも国内規模でも社会基盤の整備が求められている。すなわち,地質学はこうしたインフラテクノロジーの面で大いに貢献しなければならない。土木建設の下請としての地質調査ではなく,どこに何を何のためにどのように作るのかといったプランニングの初期の段階から地質家がタッチし,全体像に責任を負う立場に立つ必要がある。環境設計などというと神をも畏れぬ響きがあるが,地質家はアースデザイナーなのである。乱開発時代には地質調査に行くとムシロ旗で迎えられたこともあったが,土木の僕・乱開発の先兵では若者にソッポを向かれて当然である。これからは自分たちの住環境をよりよくしてくれる味方として歓迎され尊敬されるようでなければならない。そのためには従来のルーチンの地質調査に甘んじていてはダメで,土木関係者に一目置かせるような鋭利な武器を学問的に提供できる素地を今から築いていく必要がある。学際的な分野を創造していくことが急務である。変り身の早い工学方面では,環境システム工学や果ては地球工学(第11図)を唱え,次代の産業革命で主役たらんと準備おさおさ怠りない。数千万年前の古環境を論じて環境科学をやっていると称しお茶を濁すようでは,もはや地質学には未来はない。101~103年オーダーの近未来について定量的に予測し,具体的解決策を提言できる力量が必要である。「現在は過去の鍵」という時代は過ぎた。「過去は未来の鍵」と胸を張れないようではダメである。今回もバスに乗り遅れるようなら,ごく限られた理学部に博物学者を少数残しておくだけにして,工学部に地質工学科を新設するか,社会開発工学科に地質工学講座を併設するしかないであろう。
こうした新しい学問を創造していくと同時に,学会レベルでもいくつかのビッグプロジェクトを組織し,例えば重点領域研究が常時数本走っているなど,研究費の面でも若手研究者に魅力あるものにしなければならない。僅かな科研費を平等に分けよなどと,小さなパイを巡っていがみ合っているなど愚の骨頂である。今こそ地球環境を前面に立てて億単位の潤沢な研究費を要求する絶好のチャンスであろう。
②新制大学の個性化・ブロック化と実学のための教養教育
旧制大学が次代を担う研究者を養成するところであることは否定できない。ここでは地球惑星科学や前述の学際的科学の最先端を切り開く責務がある。今までの地位に安住せず頑張ってもらえばよい。講座制の狭い枠を取り払った東大地質の研究グループ制など一つの試みとして評価できよう。しかし同時に,古典的な分野についても学問的後継者を養成する義務がある。いたずらに流行を追い,トピックスにだけ飛びつく風潮は警戒しなければならない。
一方,新制大学までが旧制と同じようにすべて博士課程を持ち,ミニ東大化を夢見るのは現実的でない。前章で述べたような実態を踏まえれば,ミニチュア版どころかカリカチュア版にしかならないであろう。学位保有者がタクシー運転手をしているニューヨークの例を持ち出して,博士の質の変化を説く人もいるが,発想が後ろ向きでナンセンスである。講座費増と学位審査権なるステータスシンボルが欲しいとのエゴでしかない。
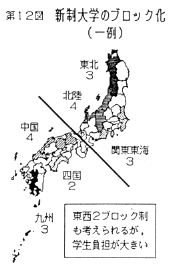 そうなると新制大学の生き残る道はどこに存在するのであろうか。新制大学はどこも実質的に複合講座で,同一分野の研究者が身近にいないのが普通である。一人でコツコツと趣味的にルーチンの仕事をこなして研究と称することのできた古き良き時代と異なり,研究はチームでする時代になってきた。最新の情報と活気に満ちた真摯なディスカッション,燃えるような雰囲気が日常必要である。そのためには少なくとも旧制大学の1講座分4人くらいは集まっていて欲しい。新制大学の教員を再配置して,各大学に個性を持たせたらどうであろうか。全国を数ブロックに分け(第12図),各大学はそれぞれの地域性に応じた1ないし2分野に重点をおくのである。九州ブロックを例にとると,熊本大は九州山地の中古生界や天草をひかえているから堆積と構造地質,鹿児島大は火山と資源,琉球大は海洋と古生物といった具合である。地球物理系は全国的地震観測網を念頭において各ブロックに一つぐらいずつ拠点校を置けばよい。こうすれば旧制大学に引けを取らないような研究拠点になり得るであろう。
そうなると新制大学の生き残る道はどこに存在するのであろうか。新制大学はどこも実質的に複合講座で,同一分野の研究者が身近にいないのが普通である。一人でコツコツと趣味的にルーチンの仕事をこなして研究と称することのできた古き良き時代と異なり,研究はチームでする時代になってきた。最新の情報と活気に満ちた真摯なディスカッション,燃えるような雰囲気が日常必要である。そのためには少なくとも旧制大学の1講座分4人くらいは集まっていて欲しい。新制大学の教員を再配置して,各大学に個性を持たせたらどうであろうか。全国を数ブロックに分け(第12図),各大学はそれぞれの地域性に応じた1ないし2分野に重点をおくのである。九州ブロックを例にとると,熊本大は九州山地の中古生界や天草をひかえているから堆積と構造地質,鹿児島大は火山と資源,琉球大は海洋と古生物といった具合である。地球物理系は全国的地震観測網を念頭において各ブロックに一つぐらいずつ拠点校を置けばよい。こうすれば旧制大学に引けを取らないような研究拠点になり得るであろう。
ただし,学生の教育面に偏りが出るのは好ましくない。ごく基礎的な教育は自前で行うとして,あとは単位互換制度をフルに活用するのである。他大学の学生と接し,自分の先生と異なる学風の先生に教わって,カルチャーショックを受けるのは何物にも替えがたいメリットの一つである。今のままではあまりに井の中の蛙であり過ぎる。こうして修士課程は他大学大学院に進学するクロス進学が通例になれば,学生の中にも活気が出るに違いない。さらにその中から研究者としての資質に富む学生が出れば,大学院大学の博士課程に送り込めばよい。もちろん,これには解決すべき問題点も多い。例えば,6月の梅雨時に各大学の演習林や臨海実験所・セミナーハウスなどを用いて集中講義月間を設けたらどうだろうか。3大学が参加した場合12科目開講されるので,学生はその中から4科目聴講するのである。専門の2ヶ年で8科目は取れる。地質見学旅行(巡検)も各大学が地域の特色を活かしたコースを設定して実施し,学生が各自好きなコースを選択すればよい。いくら大学の施設を使うにしても,学生の旅費・滞在費等かなりかさむことは避けられない。臨海実習と同様文部省から若干の補助は出るだろうし,在来生合宿研修費も使えるが,業界から基金や奨学金を募るのも一法であろう。
しかし,このような個性化は得てして研究至上主義を生み,教育を単なる雑用と考える弊害が出てきやすい。卒論なども重箱の隅をつつくようなテーマを与え,自分の研究の下請として利用する不心得者が出る恐れがある。前章で述べたような現状を考えれば,新制大学の使命は主として実社会に人材を供給することにある。アメリカにおける1970年代の大学淘汰時代を乗り切ったとして有名なブラッドフォード・プランで提唱された「実学のための教養教育(practical liberal arts education)」が参考になろう(喜多村, 1990)。地質学もこれを支えてきたインフラの変化に対応しなければならない。卒業生の就職先を考えれば,今までのような古典的地質学の教育だけでは不十分である。土木地質の場合,岩石や地層を観察するにしても,もっと物性的な見方が必要だし,そのための数学・物理の素養が欠かせない。大学教育でほとんど無視されてきた地下水など水の問題もまた重要である。地球環境を考えるには,地球科学の枠にとらわれず環境科学・生態学はもとより,社会経済全般にわたる幅の広い教養が要求される。このように主張すると,大学は職業訓練校ではないとの反論が必ず出る。しかし,鉱物の同定は鉱山業,化石の鑑定は石油や石炭産業に行くための必須技術だったのである。前時代の職業技術教育を行なっていてアカデミズムと思い込んでいるところに悲喜劇がある。こうした卑近な職業技術教育ではなく,次の時代に柔軟に対応できる幅の広い教養教育が今求められている。その点,現在文部省が推進している教養部解体路線は賛成できない。東大の他大学にない強みは,教養学部を抱え充実した一般教育が行なわれているからだといわれる。これではますます差がつくであろう。
上記の改革を実行するためには,教員の資質の向上が不可欠であることは論を待たない。文部省的自己評価とは違った意味での,自らの殻を破る厳しい自己研鑽と努力が要求される。
③フリーアドミッションの実行
学生集めに四苦八苦している現状では,どんな改革案も絵に書いた餅に過ぎないとの意見もあろう。そこで提案だが,「入りやすくて出にくい」アメリカ的なやり方を実行してみるのはどうであろうか。また,学科ごとの入試も廃止して,東大や北大のように理類ないし理学部として採用するのである。現在の高校生に人生を考え幅広い読書をする余裕はない。その結果,偏差値だけで機械的に振り分けられて学科を選択するため,どこの学科も不本意入学者を抱えて苦労している。そこで,学部程度の大分けで,講義室の許す限り定員の 1.5倍程度まで入学させるのである。今の教養部制度では一方的に教養部に迷惑をかけることになるが,幸か不幸か4年一貫教育になるから,自分たちの問題として捉らえることができる。1・2年生のうちにそれぞれの学科から出かけて行って,せいぜい魅力的な講義をして自分たちの学科にスカウトするのである。基礎教育が大いに改善されるに違いない。しかも現在のように8年間は無条件で在学できる制度は廃止し,毎年厳正なチェックを行って基準に満たない者はどしどし退学させる。もちろん,マスコミとタイアップして大々的に宣伝し,こうしたシステムを承知の上で入学させる必要がある。こうすればかなり意欲的な学生が残り,大幅なレベルアップが見込まれると思う。
3.おわりに―出来るところから実践を―
世間では「リストラ (restructuring)」なる語が流行語になっている。産業構造の再編に伴って企業が生き残っていくためには避けて通れない道だからである。学問の世界も例外ではない。地質学の分野,就中,大学ではスクラップも含む思い切ったリストラが急務である。少なくとも単位互換など出来るところからすぐにでも始めなければならないと思う。小論が討論を巻き起こす契機になれば幸いである。
しかし,優秀な学生を集めるためには大学の努力だけでは限界がある。学問の魅力だけでなく,地質家の社会的地位が高くならなければやはりいい学生は集まらない。医師など3Kそのものの職業だが,社会的名声と高収入,それに生命を救うとの使命感があるからこそ優秀な学生が医学部に集中するのである。地質調査業界の努力を切望する。
小論を書くに当たって,②については静岡大池谷氏,③については信州大公文氏に有益なご討論をいただいた。深く感謝する次第である。
[参考文献]
- 岩松 暉(1990):大学地学教育と地質調査業,応用地質,32,184-187.
- ――――(1991):国立大学地球科学系学科の改組の動きと応用地質学における後継者養成,応用地質,33, 220-226.
- 喜多村和之(1990):『大学淘汰の時代』, 中公新書, 194pp.
- 国立19大学地学教室主任会議(1992):『全国大学地球科学系教室要覧』, 98pp.
- 小宮山宏編著(1992):『地球環境のための地球工学入門』, オーム社, 212pp.
- 玉田 樹(1992):二一世紀社会と大学経営, 高等教育研究会編『大学は生き残れるか』, 119-157, 機関紙共同出版
ページ先頭|応用地質雑文集もくじへ戻る
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:1997年8月19日
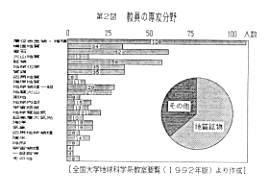
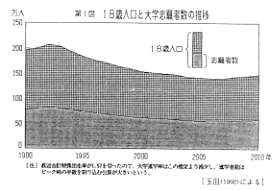 大学は今激動期にある。戦後の新制大学発足時に匹敵するという。ただベクトルは全く逆,「少子時代」を迎えて縮小整理の方向にある(第1図)。農学部・工学部の改組は大方終わり,教養部解体に伴って理学部が俎上に上っている。その上地球科学系では,89年の測地審建議・90年の国立10大学理学部長会議提言の方向に沿って地球惑星科学への転換がはかられている(第2図)。
大学は今激動期にある。戦後の新制大学発足時に匹敵するという。ただベクトルは全く逆,「少子時代」を迎えて縮小整理の方向にある(第1図)。農学部・工学部の改組は大方終わり,教養部解体に伴って理学部が俎上に上っている。その上地球科学系では,89年の測地審建議・90年の国立10大学理学部長会議提言の方向に沿って地球惑星科学への転換がはかられている(第2図)。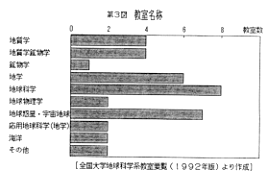 既に10大学(旧制帝大+筑波大・東工大・広島大)のうち,地質学・鉱物学の名の付く教室があるのは北大・東大・京大の3大学になってしまった(第3図)。北大・京大の地鉱教室は地球物理と合体して地球惑星科学教室への改組を検討中というから,全滅は間近い。
既に10大学(旧制帝大+筑波大・東工大・広島大)のうち,地質学・鉱物学の名の付く教室があるのは北大・東大・京大の3大学になってしまった(第3図)。北大・京大の地鉱教室は地球物理と合体して地球惑星科学教室への改組を検討中というから,全滅は間近い。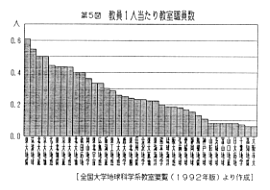
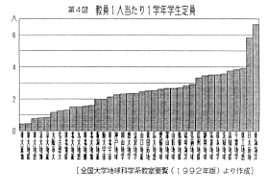 一方,欧米からの基礎研究ただ乗り論に応えると共に,国際競争に打ち勝つ技術革新を遂行できる人材を養成するため,大学院重点化構想が急ピッチで進行している。旧制大学を大幅に拡充して大学院大学にしようとするものである。新制と旧制では今までにもさまざまな格差が存在していたが(第4図・第5図),こうした大学にさらに先端科学研究費や施設整備費の重点投資が行われる。また,従来1講座当たり2名の大学院学生定員を一挙に5名に増やすことになっており,東大から順次実施に移されつつある。この結果,いわゆる玉突き現象が起きて中央への人材の一極集中が加速されている。旧制大学の間ですら院生の奪い合いが生じているのだから,前述の少子時代を勘案すると,新制大学大学院など不要に近い。
一方,欧米からの基礎研究ただ乗り論に応えると共に,国際競争に打ち勝つ技術革新を遂行できる人材を養成するため,大学院重点化構想が急ピッチで進行している。旧制大学を大幅に拡充して大学院大学にしようとするものである。新制と旧制では今までにもさまざまな格差が存在していたが(第4図・第5図),こうした大学にさらに先端科学研究費や施設整備費の重点投資が行われる。また,従来1講座当たり2名の大学院学生定員を一挙に5名に増やすことになっており,東大から順次実施に移されつつある。この結果,いわゆる玉突き現象が起きて中央への人材の一極集中が加速されている。旧制大学の間ですら院生の奪い合いが生じているのだから,前述の少子時代を勘案すると,新制大学大学院など不要に近い。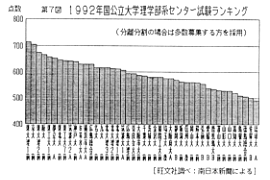
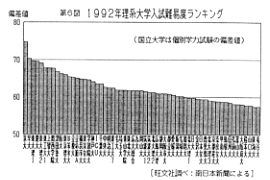 その上,受験生の文系志向・国立離れの問題がある。1990年のデータでは大学志願者の2割しか理系を希望しないという。理系は受験科目が多い上に,大学ではハードな実験や卒論がある。社会に出てからそれが報いられるのならまだしも,法経出身の経営者にアゴで使われる。これでは優秀な人材が理系に進学するはずがない。重厚長大型産業が国を興し生活を豊かにすると考えられてきた高度成長期以前の時代には,それでも理系進学者が多かった。経済のソフト化・三次産業化に伴って,若者の価値観が変るのは当然であろう。理系偏重の国立が敬遠される根源もそこにある。低廉な国立授業料というメリットが失われた今,受験生を引きつけるのは難しい。今や早慶は言うに及ばず,日東駒専なる言葉もできたように私学の優位は歴然としている。若者の都会指向と重なり,地方に存在する国立大学(いわゆる地方大学ではなく北大・九大も含む)が私学や都会の大学に優秀な人材を奪われ,激しい地盤沈下に見舞われている。第6図・第7図のようなものが堂々と新聞に発表されるから,ますますこの傾向が助長される。嗚呼。私が勤める鹿大地学科で,入学から卒業までの追跡調査を行なったことがある。以前は入試成績は必ずしもよくないが卒業時にはなかなか優秀な学生がいた。ところが,数年前から入試成績と学部での学習意欲に高い相関を示す傾向が出てきた。つまり,下位成績といっても昔と今とではレベルが違って,最近は基礎学力がないために,知的好奇心すらわかないような深刻な状態なのである。しかも地球科学に興味を持っているならまだしも,コンピュータが選んでくれた第一志望で,不本意入学者がかなりの比重を占める。元々文系志望だった者までいる始末である。その上,解法を丸暗記するのが学問だとの発想が染み付いているから,「科学する喜び」とか「自然界の不思議に感動する」といったことは全然ピンと来ないらしい。先生はいつも正解を知っていて,自分たちは練習問題を与えられているだけと信じている。したがって,何事も受け身で指示待ち人間である。卒論のように敷かれたレールのない場合には,どちらに向かって走ってよいか分らず呆然とするしかない。登校拒否など自我を持っている証拠で,まだ救いようがあるのかも知れない。一番困るのは「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則が働くことである。「赤信号みんなで渡れば恐くない」を実践するため,能力のある者までダメになってしまうのである。「こうした学生を目覚めさせるのが教員の力量というものだ」といったきれいごとを言える段階ではなくなった。要するに総じて現在の大学は,大学という名のレジャーランドに成り下がり,学問の府なる言葉が死語になって久しい。
その上,受験生の文系志向・国立離れの問題がある。1990年のデータでは大学志願者の2割しか理系を希望しないという。理系は受験科目が多い上に,大学ではハードな実験や卒論がある。社会に出てからそれが報いられるのならまだしも,法経出身の経営者にアゴで使われる。これでは優秀な人材が理系に進学するはずがない。重厚長大型産業が国を興し生活を豊かにすると考えられてきた高度成長期以前の時代には,それでも理系進学者が多かった。経済のソフト化・三次産業化に伴って,若者の価値観が変るのは当然であろう。理系偏重の国立が敬遠される根源もそこにある。低廉な国立授業料というメリットが失われた今,受験生を引きつけるのは難しい。今や早慶は言うに及ばず,日東駒専なる言葉もできたように私学の優位は歴然としている。若者の都会指向と重なり,地方に存在する国立大学(いわゆる地方大学ではなく北大・九大も含む)が私学や都会の大学に優秀な人材を奪われ,激しい地盤沈下に見舞われている。第6図・第7図のようなものが堂々と新聞に発表されるから,ますますこの傾向が助長される。嗚呼。私が勤める鹿大地学科で,入学から卒業までの追跡調査を行なったことがある。以前は入試成績は必ずしもよくないが卒業時にはなかなか優秀な学生がいた。ところが,数年前から入試成績と学部での学習意欲に高い相関を示す傾向が出てきた。つまり,下位成績といっても昔と今とではレベルが違って,最近は基礎学力がないために,知的好奇心すらわかないような深刻な状態なのである。しかも地球科学に興味を持っているならまだしも,コンピュータが選んでくれた第一志望で,不本意入学者がかなりの比重を占める。元々文系志望だった者までいる始末である。その上,解法を丸暗記するのが学問だとの発想が染み付いているから,「科学する喜び」とか「自然界の不思議に感動する」といったことは全然ピンと来ないらしい。先生はいつも正解を知っていて,自分たちは練習問題を与えられているだけと信じている。したがって,何事も受け身で指示待ち人間である。卒論のように敷かれたレールのない場合には,どちらに向かって走ってよいか分らず呆然とするしかない。登校拒否など自我を持っている証拠で,まだ救いようがあるのかも知れない。一番困るのは「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則が働くことである。「赤信号みんなで渡れば恐くない」を実践するため,能力のある者までダメになってしまうのである。「こうした学生を目覚めさせるのが教員の力量というものだ」といったきれいごとを言える段階ではなくなった。要するに総じて現在の大学は,大学という名のレジャーランドに成り下がり,学問の府なる言葉が死語になって久しい。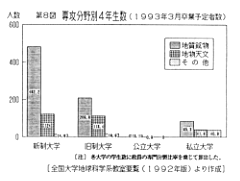 以上の問題は,わが国の地質学にとって意味するところが大きい。周知のように地質学の人材養成は主として国立大学,就中,新制大学が担ってきたからである(第8図)。第一に,大学教員の大部分を輩出している旧制10大学が地球惑星に転換することは,今後の地質学教育に重大な影響を与えることになる。恐らくフィールドサイエンスとしての地質学を教えられる人が少なくなるであろう。第二に,主として土木建設業界など実社会に人材を供給してきた新制大学のレベルダウンは,地質調査業界の技術革新にマイナスの影響を及ぼすであろう。これでは地質家の社会的地位の向上は望むべくもない。
以上の問題は,わが国の地質学にとって意味するところが大きい。周知のように地質学の人材養成は主として国立大学,就中,新制大学が担ってきたからである(第8図)。第一に,大学教員の大部分を輩出している旧制10大学が地球惑星に転換することは,今後の地質学教育に重大な影響を与えることになる。恐らくフィールドサイエンスとしての地質学を教えられる人が少なくなるであろう。第二に,主として土木建設業界など実社会に人材を供給してきた新制大学のレベルダウンは,地質調査業界の技術革新にマイナスの影響を及ぼすであろう。これでは地質家の社会的地位の向上は望むべくもない。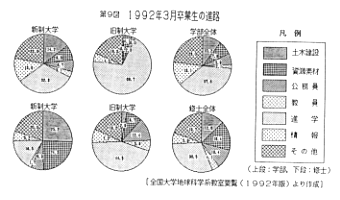 学生気質の変化も著しい。受験競争の激化に伴い,都会の進学校からしか進学できなくなったため,自然をあまり好きでない学生が増えてきた。それに少子時代,甘やかされて育ったから,額に汗して努力することを厭う者が多い。地質調査業は自然を相手にしている以上,ある程度3Kであることは避けられない。大学で学んだ専門を活かす職場に就職する者が極端に少なくなってしまった(第9図)。行管や文部省ならずとも,この行革の時代,そんな学科は潰していまえとの声が起きて当然である。恐らく大幅定員割れを起こした大学からお取り潰しの動きが出てくるであろう。レベルダウンだけでなく,実社会が必要とする人材の絶対数すら不足する深刻な事態になる恐れが強い。
学生気質の変化も著しい。受験競争の激化に伴い,都会の進学校からしか進学できなくなったため,自然をあまり好きでない学生が増えてきた。それに少子時代,甘やかされて育ったから,額に汗して努力することを厭う者が多い。地質調査業は自然を相手にしている以上,ある程度3Kであることは避けられない。大学で学んだ専門を活かす職場に就職する者が極端に少なくなってしまった(第9図)。行管や文部省ならずとも,この行革の時代,そんな学科は潰していまえとの声が起きて当然である。恐らく大幅定員割れを起こした大学からお取り潰しの動きが出てくるであろう。レベルダウンだけでなく,実社会が必要とする人材の絶対数すら不足する深刻な事態になる恐れが強い。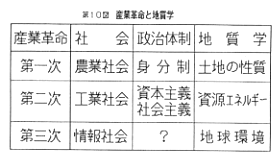 しかし,現在は学問の世界でもボーダーレス時代である。理学と工学の差が極めて接近してきた。超伝導や超LSI などナノテクノロジーはまさに物理学そのもので,基礎理論の世界でも理学が押され気味という。大型機器に頼らざるを得ないビッグサイエンスの世界のことだと軽く見るのは誤りである。社会のニーズにマッチし,社会の発展方向に沿ってそのうねりに乗った時,学問もまた発展することは科学史の教えるところである(第10図)。研究テーマにしても,社会という汲めども尽きない泉から汲み出してこそ,単なる従来の延長線上ではない斬新な発想が生まれるのだ。よく基礎研究と応用研究のバランスのとれた発展をと言われるが,IGC と日本地質学会年会の講演内容を比較すれば,日本の地質学がいかに偏っているか歴然としている。IGC におけるIUGS会長講演のような講演を日本の学会では聞いたことがない。まして大学の地質学の体系は1世紀前のままで旧態依然としている。
しかし,現在は学問の世界でもボーダーレス時代である。理学と工学の差が極めて接近してきた。超伝導や超LSI などナノテクノロジーはまさに物理学そのもので,基礎理論の世界でも理学が押され気味という。大型機器に頼らざるを得ないビッグサイエンスの世界のことだと軽く見るのは誤りである。社会のニーズにマッチし,社会の発展方向に沿ってそのうねりに乗った時,学問もまた発展することは科学史の教えるところである(第10図)。研究テーマにしても,社会という汲めども尽きない泉から汲み出してこそ,単なる従来の延長線上ではない斬新な発想が生まれるのだ。よく基礎研究と応用研究のバランスのとれた発展をと言われるが,IGC と日本地質学会年会の講演内容を比較すれば,日本の地質学がいかに偏っているか歴然としている。IGC におけるIUGS会長講演のような講演を日本の学会では聞いたことがない。まして大学の地質学の体系は1世紀前のままで旧態依然としている。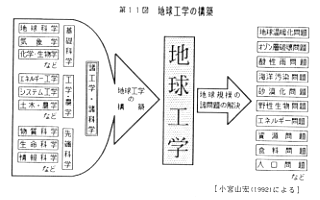 現代青年は新人類だ無気力だなどと嘲られるが,いつの時代でも青年は進取の気象に富み,意気に感ずれば目標に向かって邁進するものである。日本の地質学は若者にその目標とモティベーションを与えていない。かつて先輩たちは「山を駆け野を巡り地の幸をたずね行く,喜びを君と語らん」と誇らしげに歌っていた。石炭は黒ダイヤと呼ばれ金ヘン景気なる言葉もあった時代である。戦後復興の旗手としてもてはやされていたから,誠に意気軒昴たるものがあった。これからの時代は,自然環境と調和した持続可能な開発が求められ,物質的豊かさから真のアメニティーを追求する時代である。地球規模でも国内規模でも社会基盤の整備が求められている。すなわち,地質学はこうしたインフラテクノロジーの面で大いに貢献しなければならない。土木建設の下請としての地質調査ではなく,どこに何を何のためにどのように作るのかといったプランニングの初期の段階から地質家がタッチし,全体像に責任を負う立場に立つ必要がある。環境設計などというと神をも畏れぬ響きがあるが,地質家はアースデザイナーなのである。乱開発時代には地質調査に行くとムシロ旗で迎えられたこともあったが,土木の僕・乱開発の先兵では若者にソッポを向かれて当然である。これからは自分たちの住環境をよりよくしてくれる味方として歓迎され尊敬されるようでなければならない。そのためには従来のルーチンの地質調査に甘んじていてはダメで,土木関係者に一目置かせるような鋭利な武器を学問的に提供できる素地を今から築いていく必要がある。学際的な分野を創造していくことが急務である。変り身の早い工学方面では,環境システム工学や果ては地球工学(第11図)を唱え,次代の産業革命で主役たらんと準備おさおさ怠りない。数千万年前の古環境を論じて環境科学をやっていると称しお茶を濁すようでは,もはや地質学には未来はない。101~103年オーダーの近未来について定量的に予測し,具体的解決策を提言できる力量が必要である。「現在は過去の鍵」という時代は過ぎた。「過去は未来の鍵」と胸を張れないようではダメである。今回もバスに乗り遅れるようなら,ごく限られた理学部に博物学者を少数残しておくだけにして,工学部に地質工学科を新設するか,社会開発工学科に地質工学講座を併設するしかないであろう。
現代青年は新人類だ無気力だなどと嘲られるが,いつの時代でも青年は進取の気象に富み,意気に感ずれば目標に向かって邁進するものである。日本の地質学は若者にその目標とモティベーションを与えていない。かつて先輩たちは「山を駆け野を巡り地の幸をたずね行く,喜びを君と語らん」と誇らしげに歌っていた。石炭は黒ダイヤと呼ばれ金ヘン景気なる言葉もあった時代である。戦後復興の旗手としてもてはやされていたから,誠に意気軒昴たるものがあった。これからの時代は,自然環境と調和した持続可能な開発が求められ,物質的豊かさから真のアメニティーを追求する時代である。地球規模でも国内規模でも社会基盤の整備が求められている。すなわち,地質学はこうしたインフラテクノロジーの面で大いに貢献しなければならない。土木建設の下請としての地質調査ではなく,どこに何を何のためにどのように作るのかといったプランニングの初期の段階から地質家がタッチし,全体像に責任を負う立場に立つ必要がある。環境設計などというと神をも畏れぬ響きがあるが,地質家はアースデザイナーなのである。乱開発時代には地質調査に行くとムシロ旗で迎えられたこともあったが,土木の僕・乱開発の先兵では若者にソッポを向かれて当然である。これからは自分たちの住環境をよりよくしてくれる味方として歓迎され尊敬されるようでなければならない。そのためには従来のルーチンの地質調査に甘んじていてはダメで,土木関係者に一目置かせるような鋭利な武器を学問的に提供できる素地を今から築いていく必要がある。学際的な分野を創造していくことが急務である。変り身の早い工学方面では,環境システム工学や果ては地球工学(第11図)を唱え,次代の産業革命で主役たらんと準備おさおさ怠りない。数千万年前の古環境を論じて環境科学をやっていると称しお茶を濁すようでは,もはや地質学には未来はない。101~103年オーダーの近未来について定量的に予測し,具体的解決策を提言できる力量が必要である。「現在は過去の鍵」という時代は過ぎた。「過去は未来の鍵」と胸を張れないようではダメである。今回もバスに乗り遅れるようなら,ごく限られた理学部に博物学者を少数残しておくだけにして,工学部に地質工学科を新設するか,社会開発工学科に地質工学講座を併設するしかないであろう。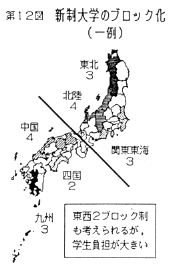 そうなると新制大学の生き残る道はどこに存在するのであろうか。新制大学はどこも実質的に複合講座で,同一分野の研究者が身近にいないのが普通である。一人でコツコツと趣味的にルーチンの仕事をこなして研究と称することのできた古き良き時代と異なり,研究はチームでする時代になってきた。最新の情報と活気に満ちた真摯なディスカッション,燃えるような雰囲気が日常必要である。そのためには少なくとも旧制大学の1講座分4人くらいは集まっていて欲しい。新制大学の教員を再配置して,各大学に個性を持たせたらどうであろうか。全国を数ブロックに分け(第12図),各大学はそれぞれの地域性に応じた1ないし2分野に重点をおくのである。九州ブロックを例にとると,熊本大は九州山地の中古生界や天草をひかえているから堆積と構造地質,鹿児島大は火山と資源,琉球大は海洋と古生物といった具合である。地球物理系は全国的地震観測網を念頭において各ブロックに一つぐらいずつ拠点校を置けばよい。こうすれば旧制大学に引けを取らないような研究拠点になり得るであろう。
そうなると新制大学の生き残る道はどこに存在するのであろうか。新制大学はどこも実質的に複合講座で,同一分野の研究者が身近にいないのが普通である。一人でコツコツと趣味的にルーチンの仕事をこなして研究と称することのできた古き良き時代と異なり,研究はチームでする時代になってきた。最新の情報と活気に満ちた真摯なディスカッション,燃えるような雰囲気が日常必要である。そのためには少なくとも旧制大学の1講座分4人くらいは集まっていて欲しい。新制大学の教員を再配置して,各大学に個性を持たせたらどうであろうか。全国を数ブロックに分け(第12図),各大学はそれぞれの地域性に応じた1ないし2分野に重点をおくのである。九州ブロックを例にとると,熊本大は九州山地の中古生界や天草をひかえているから堆積と構造地質,鹿児島大は火山と資源,琉球大は海洋と古生物といった具合である。地球物理系は全国的地震観測網を念頭において各ブロックに一つぐらいずつ拠点校を置けばよい。こうすれば旧制大学に引けを取らないような研究拠点になり得るであろう。