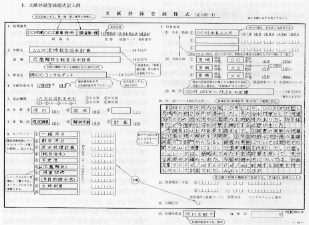
2.半公開報告書のデータベース
GeoLisは学術文献の書誌情報ですが,これとこれからお話する一次情報のデータベースの中間に,今小野さんがお話された半公開の報告書類があります。工事報告書の類は学術論文と違って事実の記載が中心ですから,いわば1.5次情報です。例えば,建設省では日本建設情報総合センターJACICでデータベースを作っています。トンネル・ダムなど建設省発注工事の報告書の抄録が引き出せ,本報告の保管場所がわかります(第1図:建設省大臣官房技術調査室, 1988)。これは1988年に開局したJACIC-NETによりNTTのDDX回線を通じてオンラインで民間も利用することができます(JACIC, 1991)。今のところ毎日更新される建設関連の各種ニュースや建設官公庁職員の人事異動速報などの利用が多く,本格的なデータベースとしての利用はいま一歩のようです。しかし,このおかげで報告書類が少なくとも1冊どこかに必ず保管されるようになったことは大変な進歩です。今後有効活用の道が開けるに違いありません。
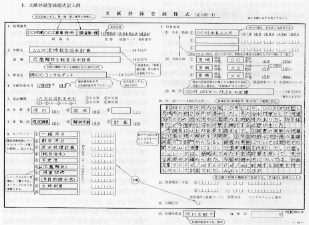
わが文部省でも,1972年に京都大学に防災科学資料センターが設置されて以来,自然災害科学地区資料センターが北海道(北大)・東北(東北大)・関東(埼玉大)・中部(名大)・関西(京大)・西部(九大)の6地区に設置され,災害科学の論文だけでなく,災害時の新聞資料や写真,対応した官庁の報告書・被害統計など災害に関するあらゆる資料を収集しております(自然災害科学・資料収集解析研究班, 1987)。こうした資料の有効利用を図るため,1982年京大に自然災害科学データベースSAIGAIKSが構築され,大学間ネットワークを通じてオンラインで検索することが可能になりました。ただし,今のところ大学関係者しか利用できません。その後,他地区センターでもSAIGAICH, SAIGAISIなど同様のデータベースが構築されています。
3.地質一次情報の重要性
さて,いよいよ地質の一次情報,つまりfact dataですが,フィールドデータなら,ルートマップ・スケッチ・産出化石リスト・ボーリングデータ・各種物探データ・各種原位置試験の計測値・観測値など,インドアデータなら,化学分析値・年代測定値・各種試験結果など,いろいろさまざまあります。このような生データは研究者個人のものとして私的所有になっており,記載論文に一部掲載される程度で,他人は見ることはできないのが普通です。本人が退職したりしたらもう所在さえわかりません。もちろん,記載のフォーマットは各人各様です。唯一例外は化石のタイプ標本で,これだけはキチンと保管されているようです。今日はフィールドデータとして地盤情報を,インドアデータとして土質試験を取り上げてみましょう。
民間地質調査業界で行っている地盤調査を例に取ってみます。毎年行われる公共事業や民需の開発に伴って,膨大な量の地質調査が行われています。大学人や地質調査所が実施する調査数の比ではありません。ボーリングだけでも総計200万本以上に達し,しかも毎年15〜16万本の割で増え続けています。その上,研究者がハンマー一丁で行う手工業的調査と違って多額の金をつぎ込み,物理探査や横坑・トレンチ調査などを併用した格段に精度の高い調査がほとんどです。しかも実際に掘削されて確かめられている例が多く,「…と考えられる」といった研究者の水掛け論とは質的に異なります。また,構造物が完成すると露頭が永久になくなり,二度とデータの取れない貴重なものもあります。しかし,残念ながら守秘義務の壁に阻まれ,一般には陽の目を見ないものが大部分で,数年もすると廃棄されてしまいます。誠にもったいないと思います。これが表に出れば,日本の地質学の発展にどれほど役に立つか知れません。
もう一つの意義は,学説は消えても事実は残るということです。一般に進論地質図は自分の目で見た通り忠実に描かれていますから,辻褄が合わず自己矛盾を起こしていることが多いのですが,自説に合わせてでっち上げた卒論や修論の地質図より後々役に立ちます。例えば,学生と長年つき合っていますと,卒論などの地質図にもいろいろ変遷があります。複褶曲地域の場合,途中の枝沢も1本1本ちゃんと詰めて追跡してみると,圧倒的に多数測られる走向方向とは斜交する方向につながるのが普通です。図学通り延長上に地層が出てこないため,昔はすぐ推定断層を引いて解決しました。露頭のない尾根に引けばバレないので尾根断層,あるいは酒の勢いで引く焼酎断層などと呼ばれたものです(笑い)。最近はmelang やolistolithなど便利な概念が出てきましたから,地層をつなぐ努力を放棄してすぐレンズや異地性岩塊にしてしまいます。同じルートマップからでもこのようにいろいろの地質図が出来上がります。断層の場合は,同じ地層と認識していたからまだよいのですが,レンズでは地層の厚さが実際より厚く見積もられてしまいます。余談ですが,枝沢まで詰めて足でつなぐ努力をしない人が増えたのは困ったことです。
地質調査所の地質図にも流行があるようです。今の5万分の1地質図の悪口を言うつもりはありませんが,昔の7万5千はよくできていて今でも使えるとの声をよく聞きます。事実に忠実に描かれているものが多いからです。小澤儀明先生は「七萬五千分之一地質圖○○を讀みて其の地域の構造を解釋す」などと読図から構造を論じておられますが,今でも同様,現在の知識で見直すとさまざまなことがよく読み取れます。地質調査所でデータベースを作るのなら,ぜひルートマップなど生データを収録していただきたいものです。5万分の1図幅自体をコンピュータに入れるのは,なるほど20万分の1のコンパイルなど所内の利用や印刷屋さんには便利でしょうが,われわれ土木地質屋にはあまり役に立ちません。やっぱり悪口になりましたかね。ゴメンナサイ。
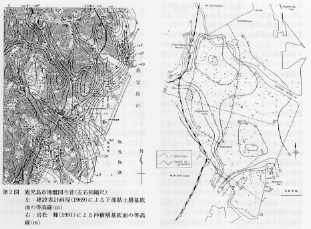
4.地盤情報データベース
地盤関係の既存のデータベースはいろいろありますが,主として官庁で作られている代表的なものをご紹介いたします。
先ず建設省では地質情報システムの構築を行っており,そのための地質調査資料整理要領やボーリング柱状図作成要領を制定しています(建設省大臣官房技術調査室, 1986a,b)。地質名をはじめすべてコード化されており,請負業者はこのコード表を提出しなければなりません。例えば,地質名は第3図のように決められており,礫混り砂質シルトは0512,シルト質砂は0320という具合です。色調も暗青灰色は*DAHなどとアルファベットで表現されます。そこで業者団体である全国地質調査業協会連合会(全地連)ではこれに対応したパソコンベースのソフトを開発しました(全地連地盤情報化委員会, 1987:矢島, 1989,1990)。もちろん,柱状図だけでなく断面図や土性図などを描く機能もあります(第4図)。全国標準仕様ですから,加盟各社のデータを集積すればすごいデータベースとなり,実用面だけでなく,学問的にもすばらしい成果が得られるのではないかと期待しています。
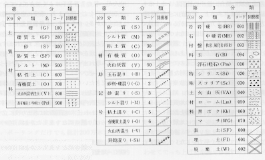

5.記載フォーマットの統一
このようなデータベースを全国的に構築するためには,何よりも記載フォーマットの統一が重要です(弘海原, 1985)。今のまま放置したら,各役所や機関ごとにバラバラのフォーマットで収録がはじまり,収拾がつかなくなる恐れがあります。施主ごとに違ったフォーマットで提出を要求される民間業者はたまったものではありません。しかも,そのデータベースの設計者が地質家でなかった場合には,恐らく地質家にとって大変使いにくいものになるであろうことは目に見えています。しかし,どんなに使いにくくても,お上のいうことは絶対ですから,従わざるを得ません。幸いJACIC様式は全地連が最初から一枚かんでおられたようですのでよいのですが,それでも例えば土質名などは地質家の使い慣れたものではなく,土質工学会の日本統一土質分類になっています。これが悪いとは言いませんが,例えば鹿児島のように,シラス地帯が後背地のところでは,みんな砂層ですから,土質工学会分類のように細砂と粗砂だけでは,一色になってしまい,対比ができません。やはりWENTWORTHの分類のように極細粒,細粒,中粒…などと細分してもらわないと困るのです。そこで鹿児島では砂層のところだけWENTWORTHも併用するよう提案しています。
軟弱地盤の沖積平野と硬岩からなる山岳地帯とでは観察記載すべき事項も違いますし,ボーリングデータと違って通常の地質調査は単純ではありませんが,やはり最低限記載を要する事項だけでも制定し,地質家にとって使いやすいフォーマットを決めて欲しいと思います。この点で地質調査所や地質学会・応用地質学会など地質の専門機関・団体がもっと積極的なイニシアチブを発揮していただきたいものです。
こうした標準フォーマットの制定はデータベースの構築にとって不可欠ですが,メリット・デメリットいろいろあります。メリットとしては記載水準のレベルアップが挙げられます。鹿児島の例で言えば,地元コンサルタントに地質出身者が少ないため,二次シラス・沖積シラスあるいは粗粒砂だけで片付けてきた人が多かった訳ですし,軽石層まで機械的に粒径で分けて礫とした人もいました。結局,オールコアボーリングを実施し,実物を前にボーリングのオペレーターに講習会を開きました。今後,質のそろった記載がなされることと思います。
デメリットとしては,マニュアル主義に陥り,それで事足れりとして,それ以上の詳細な観察や斬新な視点での見方をしなくなる恐れがあります。これは大変危険なことで,下手をすると学問の発展を阻害しかねません。心したいものです。
6.室内試験データのデータベース
次にインドアデータについて考えてみます。土質試験を例に取りますと,土質工学会は土質工学会基準JSFを制定し,標準フォーマットを作成しています(土質工学会,1991)。そのデータシートも販売しています。また,JISとして法的にも整備されていますから,民間地質コンサルタントは,当然すべてこれに準拠しています。学校ではWENTWORTHを教わっても社会に出るとJISという訳です。岩石力学試験でも日本鉱業会(現在の資源・素材学会)で標準フォーマットが制定されています(日本鉱業会岩石試験データシート作成・利用委員会, 1982)。このように工学系の学会は調査法や試験法の標準化に熱心ですが,これはデータベースの構築に直結します。これからは情報化の時代ですから,データベースのことを考えると,自分にとっていかに使いにくくても否応なしにこれに従わなければなりません。必然的にこれら学会の権威も高まります。
7.地盤情報の公開
今まで述べてきたようなボーリングなどの地盤情報や室内試験のデータベースを構築する際,問題になるのはフォーマットの統一と共に,情報公開の原則のことです。著作権法では,著作権は直接の執筆者に属すとされていますが,実際にはお金を出した施主の了解なしには発表できないのが普通です。役所は後からのさまざまな責任追及を恐れて守秘義務を課すのが実状ですから,民間ではたとえ知的所有権があっても,なかなか公表できません。民間企業自体,調査ノウハウや営業情報の流出を恐れたり,情報の独占を保持するために公開をしぶる例もあります。しかし,地下の地質に関する情報は,個々の建設工事にとって役立つだけでなく,地域住民にとっても基本的に重要な情報です。地質コンサルタントの実施する調査の多くは官公庁の発注するものですから,納税者である国民にとって当然「知る権利」があると言えましょう。地質調査結果についても情報公開の原則が適用されて然るべきだと思います。ボーリングデータなどは統一フォーマットに基づいて提出を義務づける法律でもできないものでしょうか。地質調査所がこうした法律面でもイニシアチブを発揮していただきたいものです。
8.社会的影響力の発揮―地質調査所への要望―
どうして日本地質学会や地質調査所はもう少し社会的な影響力を発揮しないのでしょうか。地質家はハンマーさげて一人で山をテクテク歩くものだからチームプレイが下手なのでしょうか。現在,地質学を支えているインフラストラクチャーは土木建設業であり,地質家の大多数がそこで働いています。学生時代地質学会や地質調査所は大きな存在ではあっても,卒業したら土質工学会や建設省土木研究所のほうが頼りになる存在なのです。私のところの大学院卒業生が,地質学雑誌は面白くないし役に立たないから地質学会をやめたと言っていました。
地質学会も大学も,そして地質調査所もいつまでも資源だけにしがみついてバスに乗り遅れ,社会の変化から取り残されたのではないでしょうか。もちろん,資源なくして産業は成り立ちませんから,資源は依然として重要ですし,地質調査所が通産省に所属している制約もよくわかりますが,ご一考を促したいと思います。地質調査所もアカデミックな研究所の域にとどまらず,行政面でも影響力を発揮できる重みのある機関になって欲しいと思います。地球科学省にでもなって,学術面だけでなく許認可権や国家資格検定権を握る強大なお役所になる気概があってもよいのではないでしょうか。役所がいろいろ細々したことまで生殺与奪の権を握る強大な官僚国家はあまり感心しませんが,日本の現状では地質家が頼れる役所がどうしても必要なのです。地質家にとって大学は生みの母ですが,一人前の社会人になってからは,頼りになり相談相手になれるのは,やはり頼もしい実力のある父親です。地質調査所はせいぜい10〜20人からなる大学の地質教室など問題にならないような陣容を誇っています。その地質調査所が,“親父”役を果たす義務があるのではないでしょうか。
最後に,情報に関して地質調査所に注文を言わせていただければ,情報収集活動とかデータベースとかを云々する前に,何よりも一次情報たる精度の良い地質図の提供が義務だと思います。5万分の1地質図幅が未だに全国をカバーしていないのではお話になりません。全国の地質家,とくに民間地質調査業界にとって最大の要望だと思います。やむなく国土庁の表層地質図を使っているのが実状です。確かにこの表層地質図はレベルが千差万別で,中にはかなり問題のあるものもありますが,それでも全然ないよりはまだましなのです。
また,私見ですが,地震や火山に関する全国的な精密観測を実施する一元的な機関が必要だと思います。わが国のような地震火山国で1大学に地震研究所があるだけというのはおかしなものです。国立の大きな地震研究所・火山研究所と同時に,専門官庁も必要です。先にも述べましたように気象庁と地質調査所を併せて地球科学省になるか,気象庁の地震火山部門を吸収して地震地質庁にでもなり,精度のよいデータを恒常的に収集していただきたいものです。台風が来たからといって機械を下げて観測に飛んで行く気象学者がいるでしょうか。毎日,百葉箱を覗いて気温や雨量を測っている学者がいるでしょうか。それは技官(オペレーター)の仕事です。気象学者は主として理論面を担当しているのです。大学の地震屋さんでこのオペレーターの仕事をして学者だと勘違いしている人がたくさんいます。しかも学閥ごとにネットが違う訳ですからお話になりません。地質調査所も純アカデミックな研究所の域にとどまらず,気象庁のような現業官庁的機能も持って欲しいと希望します。こうした観測面での一次情報の提供も地質調査所に期待したいところです。
所外の地質一次情報の収集については,すでに述べました。全国に埋もれている地質一次情報収集の中心になっていただきたいと思います。
二次情報(文献情報)に関しては,外部へのレファレンスサービスとコピーサービス,および地質図索引図のフロッピー提供などをお願いいたします。そろそろオンラインサービスも考えられたらいかがでしょうか。
以上,まとまりのない話でしたがこれで終わらせていただきます。また,地質調査所への悪口雑言ご容赦ください。先ほどのうちの卒業生のように地質学会や地質調査所を見捨てたのならこんなことは言いません。これでも地質調査所の応援団のつもりなのです。ご参考になれば幸いです。ありがとうございました。
引用文献