地質学からみた今後の日本
『21世紀の地学教育を考える大阪フォーラム報告書』16-19.
1.はじめに―20世紀と地質学―
世は激動の時代である。新世紀はどのような時代になるのであろうか。未来を見通すには過去をふり返る視点が必要である。20世紀を総括するのにいろいろな切り口があろう。科学技術面では「原子力時代」・「宇宙時代」といった言葉もある。しかし、それらをもたらしたのも人間社会である。社会からの切り口では、20世紀は「帝国主義と社会主義の世紀」だった。覇権を求めて相争う「戦争と革命の世紀」でもあった。資本主義と社会主義は一見対極にあるように見えるが、どちらも前世紀の産業革命が生み出した双子の兄弟である。共に富とパンを求めて工業化に狂奔した。科学技術も総動員され急速に発展した。「原子力時代」・「宇宙時代」もその産物である。その結果何を招来したか。地球は満身創痍となり、人類生存の危機さえ叫ばれるような事態に立ち至った。マルクスが貧しい労働者に腹一杯食べさせたいと「必要に応じて受け取る」共産主義社会を夢見たとき、人間の生産力が地球環境にまで影響を与えるとは思いもよらなかったに違いない。平成11年版環境白書は「20世紀は破壊の世紀」と決めつけている。世紀前半は自然の収奪(資源開発)であり、後半は自然の破壊(乱開発)であったという。いささか乱暴であまりに否定的な総括ではあるが、確かに資源浪費の時代であった。地球が数千万年・数億年といった長い地質時代をかけて形成した化石燃料や鉱物資源を猛烈な勢いで消費したのである。石炭鉱山や油田の廃墟に立てば実感できる。また世紀後半、社会資本の充実をめざして公共投資が精力的に行われた。奥地まで高速道路が走り、渚や湿地はコンクリート護岸に取って代わられた。都市はコンクリート砂漠と化している。一昔前と景観は一変してしまった。しかし、資源とエネルギーがあったればこそこれだけの人口を養え、社会資本が充実したからこそ豊かで快適な生活が営めたのである。さもなくば、江戸時代の生活水準のまま、人生50の短命生活を余儀なくされていたであろう。功罪ともに全面的に評価しなければならない。
それではこうした20世紀の総括と地質学はどのように関わるのであろうか。世紀前半、地質学は資源とエネルギーを担う基幹学問として多大の貢献をしてきた。4年に1度開かれる国際地質学会議(IGC)では、国家元首クラスの要人が名誉総裁を務める慣わしがある。どこの国でもそれだけ地質学が重要視されてきたのだ。わが国においても、国立研究所の第1号は地質調査所だったし、お雇い外国人教師の第1号は鉱山技師のコワニエだった。地質学は花形の学問だったのである。しかし、世紀後半、地質学を支えるインフラが資源産業から土木建設産業にシフトしたにもかかわらず、当時の日本の地質学は従来の学問的枠組みに閉じこもり、時代のバスに乗り遅れてしまった。そのため、開発の主導権は土木工学が担うこととなり、地質学はプランニングの段階にタッチできず、設計施工に必要な地盤データを集める土木の僕となり下がった。工学は歴史的視点を持たないから、現在時点での最適適応だけを考える。どうしても自然の摂理を無視した開発計画になりがちである。乱開発につながった遠因がここにある。一方、地質学は悠久の自然史の流れの中で現在を捉えるから、未来を洞察することができる。また、文字通り地球の科学geologyであり、汎世界的な視点も持ち合わせている。こうしたロングレンジの発想とグローバルな視野という地質学の長所が生かされなかったのが悔やまれる。地質学が果たすべき役割を担わなかった責任は大きい。
こうした反省の上に立って、以下今世紀、日本の地質学が果たすべき役割について考察してみたい。その前に、日本の国土の自然的特質と日本人について触れておく。
2.われわれの生活の場―日本列島の自然―
われわれの住む日本列島を日本海溝から眺めてみよう。10,000m級の山々が連なる大山脈と映るに違いない。一昔前はアルプス―ヒマラヤ造山帯の延長と言われたものだ。今では海のプレートと陸のプレートがせめぎ合うところ、環太平洋変動帯と呼ばれている。ここでは現在でも太平洋プレートやフィリピン海プレートが沈み込んでおり、世界でもっとも若い活動的な変動帯の一つである。このような大山脈の8合目にわれわれの生活の場があることを改めて自覚しなければならない。
若い変動帯ゆえに当然地震活動も活発で活火山も多い。阪神大震災、有珠山・三宅島の噴火と近年地震火山活動に伴う自然災害にたてつづけに見舞われている。石橋克彦氏の言うように、日本列島は「大地動乱の時代」に突入したのかも知れない。
同時に、若い変動帯とは地殻変動の活発なことを意味する。この200万年以降日本列島の中央部は2,000mも隆起し、険しい山岳地帯を形成した。出る釘は打たれるの原理で、地すべりや山崩れなど浸食作用が活発である。しかも日本列島は細長いから、河川は急流が多く暴れ川である。明治初頭、オランダの土木技師デレイケが「川ではない、滝だ!」と叫んだとか。ゆったりと流れる大陸の川とは全く趣が異なる。当然、土石流や洪水も多い。しかし、ガンジス川や長江の氾濫のように何ヶ月も滞留することなく、日本の洪水は一晩で引いてしまう。また、地質的に若いから、軟岩や軟弱地盤も多く、地すべりや地盤沈下の素因となっている。地質構造も複雑で活断層も多く、鉱物資源はほとんどない。エネルギー資源はわずかに石炭と水力だけと言われてきたが、石炭は石油との競争に敗れ、水力発電はもう限界に近い。
一方、日本列島はまた北西太平洋モンスーン地帯に位置している。台風の通路になり、梅雨前線が停滞しやすい。冬にはシベリア寒気団が日本海を渡ってたっぷり水分をもらい、豪雪をもたらす。したがって風水害も多いが、反面水に恵まれており、年間平均降水量は2,000mmに達する。世界の平均値が約900mmというから、「水に流す」とか「湯水のごとく」といった言葉を日常語として使える幸せを感謝しなければならない。したがって、湿潤温暖な気候と相俟って豊かな森林が生い茂り、農業に適した地である。
3.八百万の神々―自然との共生―
こうした荒々しくも豊かな自然に恵まれ、われわれの祖先は、自然の至るところに神々を見いだした。八百万の神である。自然を敬い自然を友として生きてきたのだ。森は豊富な木の実を、海や川はさまざまな魚介類を与えてくれたから、砂漠の民のように自然征服といった思想を持たなかった。排他的な一神教と異なり、すべてを受け入れる懐の深さを持っていた。今でも神棚と仏壇の両方ある家が多い。都会の団地住まいで神棚や仏壇はなくても、神社に初詣し、クリスマスを祝って、お寺の除夜の鐘を聞きながら1年を終わるのが平均的日本人であろう。こんないい加減な民はない。だから論理的思考に弱く、科学が発達しなかったのだと人はいう。
しかし、これは欠点であろうか。20世紀の科学は分析哲学全盛、対象を要素に分け、精緻に解析してきた。確かにこれによって科学技術は発展してきたが、物事を一面的に見る欠陥があった。今日の地球環境問題を引き起こした淵源もここにあるように思う。戦後、アメリカから最新の栄養学が導入され、日本食は穀物食中心でカロリー不足だと、パン食・肉食が奨励された。しかし、今や和食がヘルシーとして世界中でブームになっている。戦後の回虫退治も徹底的だった。その結果、アレルギー性疾患が蔓延したという。このように、ある側面だけから見てベストでも、大局的に見ればマイナスのこともある。もともと自然界は複雑な有機体で、どこかに手をつければ、必ずどこかに影響が出る。生物の天敵同士も互いに相手を100%打倒することはない。大抵フィフティーフィフティーで折り合う。相手の撲滅やひいてはオーバーキルまで企むのは人間だけである。これからは人間と自然との共生、人間同士の平和共存が求められている。資本主義の市場原理万能論や社会主義の革命理論にしても、あるいはイスラム原理主義にしても、平和も安寧な生活ももたらさなかった。一面的な原理主義は克服されなければならない。21世紀は多様な価値観を認め合う多元主義の時代ともいう。こうしたとき、日本的なものの考え方、行動様式の良さが再評価されてもよいのではないだろうか。今世紀は世界人口の半数を占める中国とインドが世界政治の眼になるだろうから、東洋的思考の時代が到来するかも知れない。
4.豊葦原の瑞穂の国―21世紀は農の時代―
今は飽食の時代と言われている。世界中の食材が集まり、食糧自給率は4割を切った。経済大国ニッポンゆえに円の札束を積めば何でも手に入ると思い込んでいるようだ。しかし、外国から食糧を輸入するということは、その国の土壌と水を輸入することである。本来、食料を食べた後の排泄物は再び土壌に返されて循環が成り立つ。その循環の輪を断ち切るのだから、外国の土壌はどんどん疲弊し、それを補うために化学肥料を多用する。ますます土壌は痩せ塩害も起きている。悪循環である。反対に日本では廃棄物として捨てられるから、結局周り回って日本の海は富栄養化する。赤潮など日常茶飯となった。
一方、世界人口がついに60億人を突破し、100億が目前である。今でも飢餓線上にある人が何億人もいるというのに、食糧危機は避けられない。まして、地球温暖化や砂漠化が進むと、さまざまな悪影響が出て来るであろう。水問題も深刻である。世界の大河黄河の断流現象が象徴している。耕地の増大に伴う潅漑水の増加と工業用水・都市用水の取水によって生じるのだという。パレスチナ問題にしてもイスラエルの水問題が背景にある。今世紀には水をめぐって戦争が起きるかも知れないという不気味な予言もある。
先にも述べたように、わが国は水に恵まれた国である。古事記の昔から豊葦原の瑞穂の国と言われてきた。その農業最適地の日本が減反政策を行い、食糧輸入国になっているのは、食糧安保上問題だというだけでなく、世界的に見ても損失である。飢餓に苦しむ人々の食糧を結果として奪っているからだ。国土の面積が狭いから世界の食糧基地になるのは無理としても、農業基盤を整備し自給自足を達成しなければならない。明治時代には東大に農林地質学講座があった。農林地質学・水文地質学を発展させる必要がある。こうした分野の発展途上国への知識移転こそ最大の国際貢献であろう。
なお、木村尚三郎先生は「耕す文化の時代」とおっしゃっておられる。文化cultureの語源はラテン語の「耕す」である。農業を大切にしてきたフランスのような国は、文化的にも栄え、いつの世でも世界から尊敬される国として世界史の中心に居続けたのだという。わが国もいつまでもノー政を続けていると、文化が廃れてくるのではないだろうか。文化国家として生きていくためにも農業を大切にしたい。
5.災害列島―自然災害とつき合う―
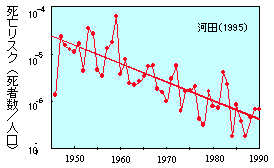 先にも述べたように、日本列島は災害を受けやすい自然的特質を有している。八岐大蛇の神話は斐伊川の洪水を意味しているという。神代の昔から日本人は自然災害に泣かされてきたのだ。これを退治した素戔鳴尊は土木技術者だったのだろうか。中国の「治水治国」と同様、災害から国民を守ることは政治の基本だったのである。時代が下って、武田信玄の信玄堤や加藤清正の川普請など、為政者は防災対策に知恵を絞ってきた。現代は、近代土木技術万能時代、湯水のように公共投資を行い、社会資本を整備してきた。その結果、阪神大震災のような都市直下型地震を除き、風水害による死者は確実に減少してきた(図-1)。しかし、これ以上ハード的に被害を減らすには費用が幾何級数的に増大する。天気予報の的中率を50%から5%上げるためには、コイン投げから観天望気に切り替えるだけでよいが、80%を85%に上げるには気象衛星を打ち上げるなど巨額の投資が必要なのと同じ理屈である。巨額の財政赤字に苦しんでいる現在、公共事業は縮減せざるを得ない。昨2000年、国も土砂災害防止法を制定して、ソフト重視に方針転換を行った。単に財政上の理由だけではない。地質学的にも重要な意味を持つ発想の転換である。
先にも述べたように、日本列島は災害を受けやすい自然的特質を有している。八岐大蛇の神話は斐伊川の洪水を意味しているという。神代の昔から日本人は自然災害に泣かされてきたのだ。これを退治した素戔鳴尊は土木技術者だったのだろうか。中国の「治水治国」と同様、災害から国民を守ることは政治の基本だったのである。時代が下って、武田信玄の信玄堤や加藤清正の川普請など、為政者は防災対策に知恵を絞ってきた。現代は、近代土木技術万能時代、湯水のように公共投資を行い、社会資本を整備してきた。その結果、阪神大震災のような都市直下型地震を除き、風水害による死者は確実に減少してきた(図-1)。しかし、これ以上ハード的に被害を減らすには費用が幾何級数的に増大する。天気予報の的中率を50%から5%上げるためには、コイン投げから観天望気に切り替えるだけでよいが、80%を85%に上げるには気象衛星を打ち上げるなど巨額の投資が必要なのと同じ理屈である。巨額の財政赤字に苦しんでいる現在、公共事業は縮減せざるを得ない。昨2000年、国も土砂災害防止法を制定して、ソフト重視に方針転換を行った。単に財政上の理由だけではない。地質学的にも重要な意味を持つ発想の転換である。
そもそも岩石が風化して肥沃な土壌が形成されると、それは力学的弱化を意味するから、表土層が適当な厚さになると山崩れが発生する。その崩土が洪水によって下流に運ばれて平野が形成され、農耕が成り立つ。もしもコンクリートで固めることによって自然を現状のまま永久に固定することが可能だとしたら、われわれの住む平野はとうの昔に海岸浸食によってなくなっているだろう。山崩れや土石流・洪水などは人類誕生以前の何億年も前から存在していた地質現象であって、なくてはならない自然の摂理なのである。われわれの祖先はそれを知っていたから、ある時は敬して遠ざかり、ある時には適当にいなしたりして、自然災害とはほどほどに仲良くつきあってきた。例えば、信玄堤は雁行状に配列しており、土石を含んだ洪水の奔流は川の中心部を流れるが、上澄みは周辺の田畑にオーバーフローするようになっている。肥沃な土壌が客土されるから、当年は不作でも翌年は豊作となる。軽くいなす例である。しかるに、近代土木技術はオランダ人から学んだ。海抜ゼロメートル地帯に住むオランダ人は、一滴も漏らすなとの発想になって当然である。以後コンクリート製連続堤防が各地に造られた。土砂流量の多い日本の河川では当然河川敷に土砂が溜まり、天井川になってしまった。鹿児島では土石流扇状地を洗出というが、藩政時代ここは耕作禁止だったとのこと。幕府から外様として締め付けられ、8公2民という過酷な税制を採っていた薩摩藩でも、僅かな年貢収入より農民を失うことを恐れたのである。敬して遠ざかる例である。われわれも祖先の知恵に学び、力ずくで自然を押さえ込む姿勢を改めるべきではなかろうか。もちろん、災害対策がソフト対策へ転換したからといって、死者が出るのは困る。地すべり・山崩れのような地質現象を社会現象としての災害にしないことが肝要である。そのためには、ハザードマップやリスクマップの整備など、事前の調査研究が重要になる。地質学の出番である。
なお、防災教育の重要性も指摘しておきたい。防災はお役所がやるものと思っている向きもある。しかし、55万都市鹿児島でも消防署員は300人である。地震で壊滅的被害を受けたとき、300人で55万人を助けるのは不可能である、第一、消防署員自身が被災者になるから、全員直ちに出動できる保障はない。「自分の命は自分で守る」のが防災の基本なのである。先年、神奈川県の丹沢で増水中にキャンプをしていて亡くなる事件があった。地学の常識をわきまえていたら防げた事例である。台湾成功大学謝教授によれば、土砂災害で亡くなるのは漢族ばかりで、少数山岳民族は自然を熟知しているから死なないという。日本でも都会人が多くなり、自然と切り離された生活をしているから、他人事ではない。また、自然災害の周期は10の2乗年のオーダーである。核家族になって祖父母からの伝承が難しくなったから、学校教育の比重が相対的に大きくなった。日本列島のような災害列島に住む者にとっては、地学は国民教養と言えよう。学校では地学のうち「自然と人間」といった章は、入試に出ないとして軽視することが多い。また野外で直接自然に触れる実験実習も少なくなっている。ぜひ改めていただきたい。
6.国土づくり・まちづくり―環境デザイン―
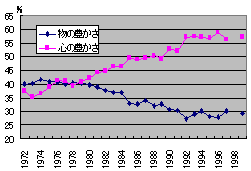 わが国は世界第2の経済大国になった。日本列島改造のかけ声の下、日本中で土木工事が行われた。新幹線や高速道路が張り巡らされ、都市には超高層ビルが林立している。街にはモノがあふれており、若者はケータイでおしゃべりに夢中。戦後の闇市は昔話、飽食時代でエステが流行る。乳幼児死亡率は激減し、長寿社会も実現した。万々歳であろうか。しかし、新聞を開くと、リストラ・過労死・少年犯罪・政財界スキャンダルと暗いニュースばかり。どこか大事なものを忘れてきたのではないか、皆気づき始めた。総理府世論調査によると、1980年を境に「心の豊かさ」を求める人が「物の豊かさ」を求める人を上回るようになった(図-2)。
わが国は世界第2の経済大国になった。日本列島改造のかけ声の下、日本中で土木工事が行われた。新幹線や高速道路が張り巡らされ、都市には超高層ビルが林立している。街にはモノがあふれており、若者はケータイでおしゃべりに夢中。戦後の闇市は昔話、飽食時代でエステが流行る。乳幼児死亡率は激減し、長寿社会も実現した。万々歳であろうか。しかし、新聞を開くと、リストラ・過労死・少年犯罪・政財界スキャンダルと暗いニュースばかり。どこか大事なものを忘れてきたのではないか、皆気づき始めた。総理府世論調査によると、1980年を境に「心の豊かさ」を求める人が「物の豊かさ」を求める人を上回るようになった(図-2)。
当然、こうした世論は長い目で見れば施策に反映される。ハード一辺倒、ハコ物づくりの国土建設計画から住民主体の国土づくり・まちづくりへである。すでに世の中はそうした方向へ変わりつつある。国土審議会政策部会第1次報告(1999)も1998年に出された新全総に基づき、「21世紀国土のグランドビジョン」を打ち出した。ここでは「地域の自立と美しい国土の創造」が掲げられ、次のような4つの戦略推進指針が提言されている。
- 多自然居住地域の創造
- 大都市のリノベーション
- 地域連携軸の展開
- 広域国際交流圏の形成
連携軸など道路網の整備といった在来型公共投資路線が見え隠れするにせよ、列島改造時代の全総とは質的に変わってきた。財政赤字と相俟って、たとえゼネコンや族議員が動こうと、公共事業が縮減される方向は変わらない。もう社会資本はかなり充実してきており、これからはストックを活用し、メンテナンスしていく時代であって、大型プロジェクト依存の時代は終わったのである。これからは心の豊かさを求める時代であり、地方の時代である。コンクリートジャングルの殺伐とした都会生活に、国民はもう十分疲れ切っている。自然回帰は必然の流れである。家庭を再構築しなければならない。
広域ローカル型社会資本という言葉がある。つまり、広域市町村程度の広がりを単位として、環境と調和したアメニティ空間を創造していく時代なのである。住み良いまちの条件としては、健康・快適・便利・安全といった4条件があげられる。ここでもアメニティが挙げられており、新全総でいう多自然型居住地域という方向とリンクする。国土交通省もコンクリートでガチガチに固める従来方式を反省して、多自然型河川工法とかエコシティーといった方向を打ち出してきた。中央省庁から地方自治体まで既に方向転換が始まっている。
こうした国土づくり・まちづくりには、環境と調和しながらいかに自然を利用していくか、環境デザインといった視点が重要になってくる。従来、環境問題というと、ややもすると「自然を守れ」と声高に叫ぶ開発反対運動のイメージが強かった。しかし、まったく自然に手をつけることなく、これだけの人口を養うことは不可能である。ラベンダーの絨毯で覆われる美瑛の丘も、もともとは鬱蒼とした原生林だった。開拓農民が営々と北の大地を切り拓いてきたからこそ、北海道は酪農王国になったのである。こうしてアイヌ時代とは比較にならない人口を支えることができるようになった。これを自然破壊と責められるだろうか。自然に手を加えれば不可避的に反作用が出てくる。メリット・デメリットを冷静に科学的に評価し、長い目で見て後世の批判に耐える判断をしなければならない。場合によっては、自然に一切手をつけない防御的自然保護(protection)が必要なこともあろうが、多くの場合、自然に逆らわず、自然のしくみを巧みに利用し、人間と自然との調和的共存(harmonious coexistence)をはかるのが本当であろう。日本自然保護協会沼田 真会長の比喩を借りれば、元金には手をつけてはいけないが、利息は利用させていただこうというものである。しかし、世界の歴史に照らしてみれば、過度の森林破壊を行った文明は例外なく滅亡の道をたどった。環境に決定的なダメージを与えることなしに、100億の人口を養う道を模索しなければならない。ここでもまた地質学の出番である。環境アセスメントも、開発阻止の武器としてだけではなく、持続可能な開発の立場からの活用が求められる。環境地質学はまだわが国では市民権を得たと言うにはほど遠い。発達が望まれる分野である。
7.産業の米―資源とエネルギー―
IT革命・E-コマースといった言葉が大流行、あたかも経済再生の特効薬かのように喧伝されている。しかし、経済のソフト化というが、マネーゲームや交易だけでは、トータルとしては何も富を生み出さない。互いのモノを交換しただけで、何も財貨を生んでいないからである。世界史を見ても、商業で世界を制覇した国は結局、世界史の表舞台から退場した。やはり、農業と製造業が根幹であることには変わりない。先に産業を興すために資源とエネルギーが不可欠と述べたが、両方ともわが国にはほとんどない。といっても、まさか前世紀のように植民地を求めるわけにはいかない。やはり、自前で資源調査を行い、新しい鉱床を発見して他国に利益を与え、その見返りとして売ってもらうしか手がないであろう。実は今もそうしているのである。先年キルギスで日本人の鉱山地質家がゲリラに捕まったことがある。このように、灼熱の砂漠で石油探査を行い、極寒のシベリアで鉱物資源を探している地質家の陰の努力があってこそ資源を輸入できているのである。資源地質学はもう不要といった論はいただけない。
8.おわりに―人づくり―
以上、今後の日本が進むべき方向について、いかに地質学が深く関わっているか、いかに重大な責務を負っているか、いくつかの分野について概観した。
最後に、次代を担う子ども達をどう育てるかが最大の課題だということを強調して筆をおく。地球にも人間にも優しく、かつ明日を切り拓くことのできるたくましい子に育つことを期待して。
ページ先頭|応用地質雑文集もくじへ戻る
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:2002年5月4日
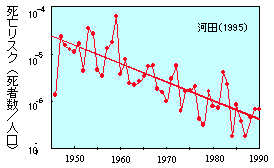 先にも述べたように、日本列島は災害を受けやすい自然的特質を有している。八岐大蛇の神話は斐伊川の洪水を意味しているという。神代の昔から日本人は自然災害に泣かされてきたのだ。これを退治した素戔鳴尊は土木技術者だったのだろうか。中国の「治水治国」と同様、災害から国民を守ることは政治の基本だったのである。時代が下って、武田信玄の信玄堤や加藤清正の川普請など、為政者は防災対策に知恵を絞ってきた。現代は、近代土木技術万能時代、湯水のように公共投資を行い、社会資本を整備してきた。その結果、阪神大震災のような都市直下型地震を除き、風水害による死者は確実に減少してきた(図-1)。しかし、これ以上ハード的に被害を減らすには費用が幾何級数的に増大する。天気予報の的中率を50%から5%上げるためには、コイン投げから観天望気に切り替えるだけでよいが、80%を85%に上げるには気象衛星を打ち上げるなど巨額の投資が必要なのと同じ理屈である。巨額の財政赤字に苦しんでいる現在、公共事業は縮減せざるを得ない。昨2000年、国も土砂災害防止法を制定して、ソフト重視に方針転換を行った。単に財政上の理由だけではない。地質学的にも重要な意味を持つ発想の転換である。
先にも述べたように、日本列島は災害を受けやすい自然的特質を有している。八岐大蛇の神話は斐伊川の洪水を意味しているという。神代の昔から日本人は自然災害に泣かされてきたのだ。これを退治した素戔鳴尊は土木技術者だったのだろうか。中国の「治水治国」と同様、災害から国民を守ることは政治の基本だったのである。時代が下って、武田信玄の信玄堤や加藤清正の川普請など、為政者は防災対策に知恵を絞ってきた。現代は、近代土木技術万能時代、湯水のように公共投資を行い、社会資本を整備してきた。その結果、阪神大震災のような都市直下型地震を除き、風水害による死者は確実に減少してきた(図-1)。しかし、これ以上ハード的に被害を減らすには費用が幾何級数的に増大する。天気予報の的中率を50%から5%上げるためには、コイン投げから観天望気に切り替えるだけでよいが、80%を85%に上げるには気象衛星を打ち上げるなど巨額の投資が必要なのと同じ理屈である。巨額の財政赤字に苦しんでいる現在、公共事業は縮減せざるを得ない。昨2000年、国も土砂災害防止法を制定して、ソフト重視に方針転換を行った。単に財政上の理由だけではない。地質学的にも重要な意味を持つ発想の転換である。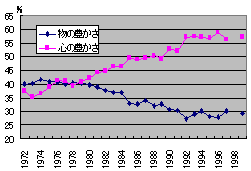 わが国は世界第2の経済大国になった。日本列島改造のかけ声の下、日本中で土木工事が行われた。新幹線や高速道路が張り巡らされ、都市には超高層ビルが林立している。街にはモノがあふれており、若者はケータイでおしゃべりに夢中。戦後の闇市は昔話、飽食時代でエステが流行る。乳幼児死亡率は激減し、長寿社会も実現した。万々歳であろうか。しかし、新聞を開くと、リストラ・過労死・少年犯罪・政財界スキャンダルと暗いニュースばかり。どこか大事なものを忘れてきたのではないか、皆気づき始めた。総理府世論調査によると、1980年を境に「心の豊かさ」を求める人が「物の豊かさ」を求める人を上回るようになった(図-2)。
わが国は世界第2の経済大国になった。日本列島改造のかけ声の下、日本中で土木工事が行われた。新幹線や高速道路が張り巡らされ、都市には超高層ビルが林立している。街にはモノがあふれており、若者はケータイでおしゃべりに夢中。戦後の闇市は昔話、飽食時代でエステが流行る。乳幼児死亡率は激減し、長寿社会も実現した。万々歳であろうか。しかし、新聞を開くと、リストラ・過労死・少年犯罪・政財界スキャンダルと暗いニュースばかり。どこか大事なものを忘れてきたのではないか、皆気づき始めた。総理府世論調査によると、1980年を境に「心の豊かさ」を求める人が「物の豊かさ」を求める人を上回るようになった(図-2)。