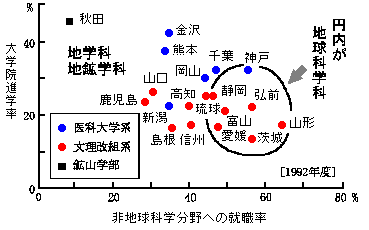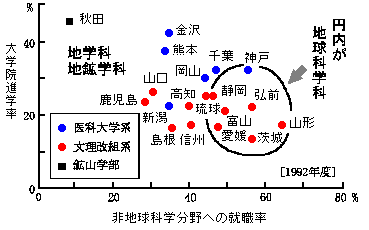岩松 暉(『応用地質』36巻2号,173-177,1995)
1.はじめに
1991年に大学審議会による“大学の大綱化”の答申が出されて以来,どこの大学でも教養部廃止・4年一貫教育を主眼とする組織改革が進行している。旧制大学は前報1)で論じた方向に改組が進行し,その多くはすでに大学院大学に移行した。やや遅れて地方新制大学でも急ピッチで改革が進行している。しかも,地学科の廃止などスクラップ化がかなりドラスティックな形で強制されており,地質学教育にとっても看過できない事態を招来している(表-1)。とくに応用地質関係業界は人材の供給を新制大学に頼ってきただけに影響も大きい。ここで現時点での情勢を,主として国立大学理学部系を中心に概観してみたい。
表-1 新制大学理学部地学系学科の改組
---------------------------------------------------
◎旧医科大学系大学
新 潟 地質科学科+自然環境科学科
千 葉 地球科学科
神 戸 地球惑星科学科
岡 山 地球科学科
金 沢 地球学科
熊 本 地球科学科
◎文理学部改組系大学
<理学部6学科体制>
信 州 地質科学科+物質循環学科
富 山 地球科学科+生物圏環境科学科
<現状5学科体制維持>
山 形 地球環境科学科
<理学部4学科に縮小>
静 岡 生物-地球環境科学科
<3学科に縮小>
茨 城 地球生命環境学科
山 口 化学-地球科学科
愛 媛 生物-地球科学科
鹿児島 地球生命科学科
琉 球 物質海洋科学科
<理工学部へ移行>
島 根 地球資源環境学科(含自然災害工学大講座)
高 知 地球圏科学科+環境防災学科
弘 前 宇宙地球理工学科
-----------------------------------------------------
(注) 下線の大学は平成8年度以降の予定案
2.大学をめぐる客観情勢
確かに今回の組織改革は先の大綱化の方針に端を発していることは事実である。これをもって文部省主導の改革と見ることもできよう。しかし,もう少し大局的に見れば,遅かれ早かれ改革に直面せざるを得ない時期に来ていた。大学令以来1世紀余,新制大学発足から半世紀,大学は制度疲労の極に達している。大学は19世紀の学問体系を前提に組織されており,新しい世紀の付託に応えるにはあまりに古い革袋になってしまった。理・工・農・医といった1文字の学部のほとんどは前世紀に出現しており,例えば理学部の数・物・化・生・地の5学科体制もまた当時の帝国大学時代に出そろったものである。しかし,今日はボーダーレス時代,学際的な研究は日常となっている。最近流行の超伝導にしても,原子のオーダーの話であって,もはや物理学そのものである。理・工の区別がつかなくなってきた。エイズにしても医学者と免疫学者・生物化学者が共同して追究している。実学は二流の学問だとか,単なる技術であって学問ではない,などとお高くとまっているのは時代錯誤もはなはだしい。パラダイムシフトが求められている時代なのである。
一歩大学の外に出れば,世はリストラばやり,産業界では円高・不況の二重苦に生き残りをかけて熾烈な減量作戦を展開している。しかし,これは一時的な不況対策ではない。力を盛り返し始めた欧米と激しく追い上げるアジア諸国に挟撃されている日本が,こうした世界経済の構造的な変化に対応しようと苦悩している姿である。学界も同様,21世紀を目前に,どこの学会も将来構想検討委員会を発足させ脱皮を図っている。学会誌の体裁をあか抜けしたものに変えたり,学生向け講座を設けたり,名称すら変更したところもある。産業界や学界だけでなく,どこの分野も新しい世紀における飛躍を狙って模索しているのだ。いわば普遍的な世紀末現象である。大学だけが埒外でいてよいはずがない。
では今日の社会情勢はどのような大学を要求しているのであろうか。ひるがえって戦後日本の歴史を振り返ってみよう。日本人は,敗戦の疲弊から立ち直るや,先進諸国に追いつき追い越せを合い言葉に,ただただがむしゃらに企業戦士として働いてきた。欧米のパテントを買ってきて“軽薄短小”に加工し,それを輸出することによってキャッチアップを果たした。その過程で新制大学の果たした役割は大きかった。旧制大学は本来官吏養成機関で文系の比重が高かったため,新制大学は理系中心に組織され,大量の技術者層を供給したからである(もちろん,その他に教員養成機能もあった)。単純労働しかしない欧米のブルーカラーと違って,格段に優秀な人材が産業界に投入されたのだ。彼らが安価で使いやすい優れた商品を開発してきたのである。しかし,今や日本はトップランナー,世界一の経済大国である。もはやお手本はない。パソコンを例に取ろう。単なる石に過ぎないICメモリなどは日本の独壇場だが,ソフトの塊,つまり頭脳の所産である中央処理装置(CPU)はすべてアメリカに握られているのだ。世界に冠たる日本製パソコンも,心臓部のCPUは全部インテル社製であり,ソフトを動かすオペーレーティングシステム(OS)もマイクロソフト社製なのである。こんな状態に甘んじている訳にはいかない。発展途上国の技術水準が低い間はまだしも,アジアの新興工業地域(NIES)が急速に追い上げており,単なる加工技術の優位性にだけ頼っていたのでは,賃金の圧倒的に安いこれら諸国に負けてしまうのは明らかである。トップの宿命として,常に付加価値の高い新技術を開発し続けなければならないのである。独創性がキーワードになる。
就業人口を研究開発職・技術職・営業職に三分するとしたら,これからは第一の研究開発職を抜本的に強化する必要がある。その方策として考え出されたのがCOE(Center of excellence)構想であろう。旧制大学を大学院大学化して巨額の資金を重点投資し,ノーベル賞クラスの頭脳を養成しようとするものである。確かに日本の国力にしてはノーベル賞受賞者数は極端に少ない。だが,こうしたやり方はかつての社会主義国が,国威発揚を狙ってオリンピックの金メダルを獲得するために,ステートアマを養成した方法に酷似している。即席効果はあるかも知れないが,長い目で見た場合得策か問題が多い。
一方,第二の技術職の多くは不要になってきた。ロボット化・マイクロエレクトロニクス化だけでなく,円高に伴う産業空洞化の進行によって,発展途上国や旧社会主義国の安い労働人口に肩代わりされるようになってきたからである。この部分を担ってきた新制大学はどのようにすればよいのであろうか。NIESに負けないためには,修士課程に比重をおいた実学中心の高度職業人養成機関となるべきであろう。しかし,今までのような大量の卒業生は不要である。その上今は少子時代,ただでさえ大学は余ってきた。それに消費税値上げの前提として行政改革を求める世論が強い。200兆円を超す財政赤字をかかえて,小さな政府への再編成は至上命題でもある。公務員を大量に抱えていて民営化になじむところは,国立病院・国立大学と郵便局が挙げられる。国立病院の民営化はかなり進んで,もう切れるところは少なくなった。郵便事業は収益をあげているが,一方的な出費があるのは国立大学である。先の世論に対する配慮からも,ある程度トカゲの尻尾切りもやむを得ない。新制大学の一部を整理民営化すれば,一石二鳥というものだ。第三セクターの教養大学にして笑顔を売るセールスマン・営業職を供給すればよい。あるいは,高齢化社会をにらんで,カルチャーセンターにするのも手である。公民館の教養講座では満足できない高学歴のお年寄りが増えているからである。
3.文部省の大学政策
こうした社会的背景もあって,文部省は大学改革を強引とも言える形で推し進めてきた。しかし,そのやり方は一律ではなく,従来からの序列に従って露骨な種別化が行われている(表-1)。序列とは,古くから博士課程大学院を持っていた旧制大学や高等師範系の大学,新制大学発足当時から理学部を持てた旧医科大学系大学,旧制高校と師範学校を母体として戦後大学に昇格した大学の3種である。理学部長会議を例にとると,旧7帝大と筑波・広島の両高等師範および東工大からなる10大学理学部長会議,千葉・新潟・金沢・神戸・岡山・熊本の旧6医大に旧女高師のお茶の水を加えた7大学理学部長会議,旧文理学部を改組して最近理学部が設置されたその他の大学からなる15大学理学部長会議の3種類ある。もちろん,後2者の新制大学が集まる22大学理学部長会議や全部集まる全国理学部長会議などの組み合わせもある。
この3種類に応じて,改革の内容も明瞭に異なる。前述のように,旧制大学は学部教授会を廃止して大学院を基礎組織とする大学に改組されたか改組中である。当然,校費も大学院が基準となるから大幅アップした。大学院は修士課程と博士課程の積み上げではなく,博士課程一本となり,前期課程・後期課程に分けられている。これらの大学の中でも差別があり,一般教育を担当するところが学部として存続できたのは東大・京大だけである。東大はその上,大学院生の教育義務まで免除され研究に専念できる先端大学院の設置も目指しているという。
旧医大系大学は,文系学部が人文(法文)学部一本だったものを法・文・経の3学部にそれぞれ独立させると共に,理系には,旧制のような縦割り大学院ではなく,理・工・農一体となった総合大学院という名の博士課程大学院を付けた。現在,従来あった修士課程を廃止して前・後期制の博士課程大学院に改組中である。もちろん,学部が基礎組織であることは従来通りで,この点が大学院大学と異なる。なお,大綱化の方針にいち早く応じて教養部を廃止し率先改組した新潟大学は,自然環境科学科が新設されて理学部6学科体制となった。
三つ目の戦後昇格組は,医大系大学に10年ほど遅れて理系に修士課程大学院ができたが,博士課程大学院は,数大学の農学部が連合して大学院を作る連合大学院しか認められなかった。ごく最近になって工学部に単独の博士課程大学院が設置された。理学部には博士課程がなく,出来たとしても工学部に付属した形での理工系研究科しか認められないだろうという。このクラスの大学では,改革の遅速に応じて信賞必罰,アメとムチ,さらに種別化が行われようとしている。率先改組組の信州・富山の両大学には学科増が認められ,6学科と拡張した。その次の年度に改組したところは,5学科の現状が認められた(静岡・山形)。ただし,静岡は1995年に入ってから4学科に縮小を指示され,地球科学科は生物学科と合同して生物-地球環境科学科になるとのことである。文部省の方針に抵抗したり,学内世論が分裂してもたもたした残りの大学には,一律3学科縮小の方針が提示された。茨城・山口両大学が平成7年度からそのように改組される。最後に残った愛媛・鹿児島・琉球は平成8年度以降になるが,この概算要求にすら間に合わなかったところは,さらに過酷な改組が強要されるであろう。例えば,生物学科は農学部へ,他は工学部へ吸収併合といった理学部廃止案さえ考えられる。追試問題ほど難しくなるのが文部省のやり方だからである。さらに,工学部を持たなかった島根・弘前・高知の3大学は,理学部を原資に理工学部設置が図られている。前述のボーダーレス時代をにらみ,新制大学を実学中心に改組しようとする動きの先取りであろう。
4.地質学分野における改革の現れ
大学院大学においては,前報1)で述べた地球惑星科学の方向への転換がほぼ完了した。文部省にとって東大は聖域なのか,ここだけは元のまま地質学教室が存在しているが,実質はフィールドサイエンスからほど遠いものになっている。しかも卒業生で地質系の会社に就職する人は少ない。例えば,本年1995年の東大卒業生12名のうち,就職は2名で保険会社と商事会社であった。もちろん,地球や惑星で起こる事象を物理化学的ないし先端科学的に究明し,グローバルな視座に立って考察することが重要なことは論を待たないが,大学教員の主要な供給機関である大学院大学がこのようなタイプの研究者だけを輩出するとなると,新制大学までがこうした方向に変化していくのは必至である。とくに,従来地質調査法の実験実習は若い教員の担当と相場が決まっていたが,最近ではこれを担当できる人が少なくなってきた。野外調査の重要性を認識し指導もできる人はそろそろ中年から初老に近づき,体力的にきつくなりつつある。地学科ないし地球科学科を卒業しても,野外調査のできる人がほとんどいないといった事態が早晩出現するであろう。
前・後期制博士大学院の設置が認められた旧医大系大学は,研究もできる大学として生き残るためには,必然的に大学院大学の方向に追従せざるを得ないであろう。さもなくば,教えるだけの教養大学への転落が目に見えているからである。既に神戸大学は地球惑星科学科に改組したし,他も地球科学科ないし地球学科へ改称しようとしている。従来でも,地学科を名乗るところに比べ,地球科学科を名乗るところは,卒業生が学生時代の専門を生かす職業に就かない割合が大きかったが(図-1),今後はますますそうした傾向が強くなるであろう。ただ一つ新潟大学だけが地質科学科に改組した。新設の自然環境科学科に一部移籍したことに伴うものである。
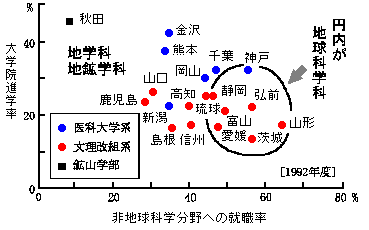 図1 新制大学地学系学科卒業生の進路
図1 新制大学地学系学科卒業生の進路
戦後昇格組の中で率先改組し6学科体制になったのは前述の通り信州・富山の両大学である。前者は物質循環学科,後者は生物圏環境科学科がプラスされた。現状5学科を維持できた静岡・山形両大学のうち山形は地球環境学科に改称された。
3学科に縮小を強要されたところは,ほとんど数理科学科と物理・化学の複合学科および生物・地学の複合学科の組み合わせになろうとしている。地学系のほとんどは,地球生命環境学科(茨城),地球生命科学科(鹿児島),生物-地球科学科(愛媛)といった名称になるらしい。例外は山口・琉球の両大学で,山口大学は化学と地学が合体した化学-地球科学科になり,琉球大学は物理学科と合体して物質海洋科学科になるという。どう考えてもあまり必然性のない学科編成である。「学問の将来像など考えて練れた案を」と要求してきた文部省が,このような改組を認めたとなると,縮小を指示された理学部はどうでもよいと軽く見られていることを意味する。教育公務員特例法で身分が保障されているため解雇できないので,当面便宜的に入れておく入れ物に過ぎない。端的に言えば清算事業団である。いずれは社会のニーズの動向や学生の進学希望などに応じて自然淘汰されるに違いない。そのために大講座制にして流動化が可能なようにしてあるのだ。
地球生命科学であれ何であれ,複合学科になる以上,学生には両方のカリキュラムが与えられるから,当然内容は薄まってしまう。従来通りの地質屋を養成することは不可能である。また,そうすべきではない。新しい看板で学生を募集しておき実態が違うとなれば,世間と学生に対する背信行為である。地球環境学講座と銘打っておきながら実際は今まで通り古生物学を講じているのが羊頭狗肉として非難されると同じである。やはり学問として新たなジャンルを開拓しなければならない。地球生命科学科の場合,地学と生物学の両方に明るい新しいタイプの人材を世に送り出すのが使命であろう。地学系の大講座を選択した学生は地学に若干軸足をおくのは当然だが,卒業後はさしづめ環境コンサルタントに就職することになるだろう。地質コンサルタントも最近は環境調査にも取り組んでいるところが多くなったから,それはそれで歓迎される人材になるに違いない。しかし,土木地質学ないし応用地質学分野の人材は育たない。生物系となると,高校時代に物理をとった学生はまず来ないし,女性が多くなるのは火を見るより明らかである。どちらかと言えば数学の嫌いな文系センスの学生がほとんどになるからである。それに,5学科全部そろった大学と3学科しかない大学としてランクの違いが天下に明白になった訳だから,優秀な受験生が集まるはずがない。
理工学部に移行する大学の中では,島根大学は地質学科が地球資源環境学科になり,新しく自然災害工学大講座が設置される。高知大学は地球圏科学科と環境防災学科が設置され,弘前大学は宇宙地球理工学科になるらしい。本来,応用地質学は理・工の学際的な分野であるから,上記のような理工学部で数学・物理に強い応用地質向きの学生が育つ可能性がある。従来の工学部と同様,入試に数学・物理を課すかどうかが鍵になるが。
5.応用地質学教育の危機的状況と学会・産業界
今までも,理学部では応用地質学教育は冷遇されてきた。山本荘毅2)が「応用地質学は大学教育の基盤をもたぬまま…(中略)…自学自習の前進を続けた」と述べているとおりである。実際,国立大学理学部で応用地質学講座の教授は筆者唯一人である。その講座も上記の事情で廃止され,ついに皆無となる。しかし,応用地質学だけでなく,前述のように地質学教育そのものにとっても危機的状況が招来している。大学院大学が頼みにならなくなって久しいから,地質調査業など産業界は新制大学卒業生に依拠して成り立っていた。その新制18大学のうち5大学で地学科は廃止されたのである。結局のところ,地質科学科を名乗る新潟・信州両大学と理工学部に移行し地質の比重の大きい島根・高知の両大学くらいが地質屋の主要な供給源となるだけであろう。あとは地球科学科ないし地球環境学科がどの程度“歩ける”地質屋を養成するかに期待するしかない。
しかし,前章で述べたような理由で,新制大学に大学院大学の雰囲気が波及するのは必至だし,業績主義であおられれば野外調査を主とする研究は圧倒的に不利だから,事態がますます深刻な方向に推移するのは致し方ないであろう。もはや理学部に頼れないとなると,島根のような理工学部を新設するか,あるいは従来の工学部に地質工学科を新設するか,土木系学科に地質工学講座ないし地盤工学講座を設けて,土木地質の専門家を養成するしかないであろう。本来なら地球時代を迎えた今日,しかも自然災害の多いわが国において,地球科学部や地球システム工学部のような学部があってもおかしくないのだが。しかし,行政改革が叫ばれている時,拡充新設をうたうこのような案は現実的には実現困難である。
一方,企業の社内研修(OJT)も,前提となる終身雇用制が崩れつつあるから割に合わない。結局,前報1)で提案した業界立研修センターを作り,民間で独自に地質技術者を養成する道しか残っていないと考える。応用地質学会や全国地質調査業協会連合会・建設コンサルタント協会など関係各位の真剣なご検討を要望したい。
参考文献
- 岩松 暉(1992): 国立大学地球科学系学科の改組の動きと応用地質学における後継者養成.応用地質,Vol.33, No.3, pp.220-226.
- 山本壮毅(1988): 日本における応用地質学の歩み.応用地質,Vol.29,No.1 ,pp.26-31.
ページ先頭|応用地質雑文集もくじへ戻る
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:1997年8月19日