岩松 暉・原口 泉(鹿大法文学部)
第29回土質工学研究発表会(1994年)特別セッション講演集, 21-26.
1.はじめに
自然災害はいにしえの昔から存在していた。今ほど科学技術が進んでいなかった時代、当然自然を力で屈服させるような強引な発想はなく、一面では避け一面では軽くいなし、ほどほどにうまくつき合ってきた。ある意味では自然災害と共存してきたのである。ハード万能主義全盛時代の今日、歴史を振り返り祖先の知恵に学ぶのも有意義なのではないだろうか。何となれば、山崩れ・河川の氾濫といった自然現象はどんなテクノパワーを以てしても防ぎ得ない自然の摂理だからである。山に樹木が緑豊かに繁るとき地面の下では風化が進行し肥沃な土壌が形成されている。この土壌が一定程度厚くなると崩壊し、洪水によって下流に供給される。こうして平野が形成され海岸侵食が防止されるのだ。地質学でいう堆積輪廻の一過程である。このような地質現象が土砂災害・水害に発展しないようにするためには、ハード的な対策と同時にソフト的な対応も極めて重要である。しらすのような特殊土壌が広く分布し、かつ台風常襲地帯でもある南九州は自然災害の多い土地である。こうした地形地質の特徴に応じた独特の社会構造が築かれ、災害文化を生み出してきた。“しらす文化”とも呼ばれる。今回は時間の関係上鹿児島市を中心に祖先の自然災害とのつき合い方を見てみよう。
2.鹿児島平野の成り立ちと縄文・弥生遺跡
縄文海進期には鹿児島平野の大部分は海で、しらす台地が海食崖で直接海に面していた。したがって、縄文遺跡群は当時の汀線、現在の平野縁辺部に点在している。いわゆる狩猟漁労の生活をしていたのであろう。その後の海退に伴って、鹿児島平野は旧田上川(江戸期に運河で新川に結ばれ流路変更されている)の扇状地として形成されたといわれる。鹿児島市内を流れる一番大きな川は甲突川(二級河川)であるが、現在の中心街は甲突川の氾濫原で低湿地帯であった。弥生の遺跡群は平野縁辺部の微高地(郡元・大竜地区など)や自然堤防などに立地している。鹿児島大学構内にある荒田遺跡でも田上川の水を導いて潅漑した井堰の遺構が発掘されている。災害に対しても安全で、かつ水の得やすいところを選んだのであろう。
なお、前述のしらす海食崖はこれ以降陸上での侵食にさらされてやや傾斜が緩くなり40゜~50゜程度になった。ちなみに現在も活発な海食が続いているところでは70゜~80゜である。これが崩壊輪廻の周期を規定しており、前者は80~100年、後者は20~30年に1回ほどの周期で崩壊が発生している。
3.島津氏の入城
鹿児島県は神話の国である。熊襲・隼人が活躍し大和朝廷に抵抗したところ、多くの古墳と陵墓がある。しかし、それも肝属川・川内川など大きな河川(一級河川)があって穀倉地帯だったところが舞台であった。猫の額ほどの平野しかなかった鹿児島市域が歴史に登場するのは中世になってからである。鎌倉期薩摩・大隅両国(後に日向国も)の守護職となった島津氏が5代貞久の時1343年に鹿児島の地に居城を構えた後のことである。鹿児島は両国の中間に位置し、双方ににらみを利かすのに都合がよかったのであろう。当初島津氏は今の上町地区にある東福寺城(多賀山)に拠った(図1)。ここは吉野台地の南端にあり、北方から攻めるには姶良カルデラ壁の隘路(現在の国道10号線)しかなく、肥後方面からは河頭の峡谷(現在の国道3号線)を通るしかない。この2箇所さえおさえておけば守備は完璧である(海からの敵には不沈艦桜島に水軍を配し背後を突く態勢になっていた)。多賀山は両方に出撃するには誠に地の利を得ている。1993年の豪雨災害で両者とも寸断され鹿児島市は「陸の孤島」と化したが、まさに島津氏の慧眼が的中した形であった。災害危険地帯であることは防衛上の利点だったのである。つまり、鹿児島市は山城に立てこもりゲリラ的に出撃する中世の戦闘様式に適合した砦に出自があり、基本的には中世の守護町が拡大したものである。今日の鹿児島の悲劇の原点がここにある。本来54万都市が立地するのは本来不向きなところなのである。
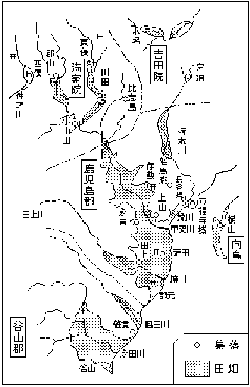 図1 南北朝時代の鹿児島
図1 南北朝時代の鹿児島
その後近世になって18代家久が中世の上山城を取り込んだ平山城としての鹿児島(鶴丸)城に移転した。帰化中国人易学者江夏賢の縄張り(設計)による本格的な都市計画であった。この時、城の前から湾にそそいでいた甲突川を南方の現在の川筋に付け替え、左岸側を新城下町の中心域としたのである。しかし、前に海を控え、背後をしらす崖に囲まれた地形的宿命は変え難い。
4.自然災害に対処する江戸期の土地制度
このように鹿児島は災害危険地帯に立地しているとはいえ、住んでいる以上災害に対処し食べていかなければならない。しらす土壌で地味が痩せ、水田に不適な農業生産性に乏しい土地である。しかも毎年のように集中豪雨があり台風に襲われる。さつまいもや大豆・粟などの畑作に力を入れたのも窮余の一策だったに違いない。「しらす畑にゃよう、カライモ(さつまいものこと)植えろよ、台風が吹いたとてさあ、土の中よ」という訳である。もう一つが琉球・奄美の収奪と南方貿易であることは言うまでもない。本来の稲作は小規模集約でいくしかなかった。庄内平野のように「本間様には及びもせぬが、せめてなりたや殿様に」と唄われたような富農は出るべくもない。等しく貧しいのである。そこで土地割替制度(門割制度)が取られることとなる。固定した私有地を耕作するのではなく、クジで数年ごとに土地を割り当てる制度である。災害危険を均等負担しようとの発想であろう。その際特筆すべきことは、洗出と呼ばれるしらす台地を穿つ谷筋を避けて割り振ったことである。ここは土石流の通路であり、こんなところを農地にしたら壊滅的打撃を受けることを経験的に知っていたからである。
また、薩摩藩の土地制度には門地・浮免・抱地・永作地・溝下地なる特色のある土地種目が存在する(桐野,1988)。前2者は古田と呼ばれ、大部分中世までに開発されたもので、他は藩政中期以後開発された新田である。門地は藩財政の基盤をなす農地で、百姓に門の組織を作らせ、強制耕作をさせていた。浮免は門高に編入せられざる自作自収の熟地で士族給養の田畑である。こうした古田は水が得やすく耕作条件のよい低地や低台地あるいは迫(谷底平野)に立地する。同じ迫でも台地からの湧水に恵まれた周辺部に先ず門地が営まれ、水害に遭いやすい河川周辺は近世になってから門地に組み入れられた。抱地は士族身分に限り認められた私有地、永作地は士民の自費仕明による農地で租納の義務のある永代作職の蔵入地、溝下地は不毛の地を士民が自費仕明した農地で10年程度無税にした後見掛にする不熟地を意味する。門地・浮免の残存地に開発されたものであるから、当然のことながら耕作条件が悪い。災害に対して安全なしらす台地上は、数10m以上も井戸を掘って牛馬でつるべを引かせなければ水が得られないし、水の得やすい山間の谷頭部は災害をまともに受けやすい。「災害の階級性」がここにも表れているが、祖先が災害のことを熟知していた証左でもある。
その他、薩摩藩独特の制度に外城制がある。薩摩藩は全国比率の6倍にも及ぶ膨大な士族を抱えていた。外様大名であるから旧領安堵されたとはいえ安心できない。いざという時には力で対抗しようと有事に備えたのであろう。77万石、天下第二の雄藩と言われたが、しらす台地ばかりで実質は貧しい。こうした家臣団を養うためには屯田制度を実施せざるを得なかった。平素は農耕に従事し、一朝事ある時には出城に拠って戦闘配置についたのである。このような下級士族は郷士と呼ばれ、鶴丸城下に住む城下士と区別されたが、同時に百姓より上に立つ士族として遇し、その集落を麓 と称した。差別を持ち込むことによって百姓一揆を押さえつけ民を支配する巧妙な手段でもあった。薩摩の小京都として名高い知覧武家屋敷群は麓集落の典型である。麓は中世の山城の近傍(麓)に立地していることが多い。交通の要衝にあり、かつ水が得やすく農耕にも適している。一国一城令が厳格に守られていた時代にどうして薩摩だけが例外を認められていたのであろうか。当然幕府は巡見使を派遣し、出城を破壊して堀を埋め元の山野に還すよう要求してきた。その時、薩摩藩は「城ヲ崩シ堀ヲウメ、其土田畑ヲウヅム時ハ、飢ニ及バン事不便ナレバ…」と弁解した。城を崩すと土砂災害が起きて田畑が荒れるからというものである。苦肉の策だったかも知れないが、なかなか巧い口実を持ち出したものだ。自然災害を外交の駆け引きに使ったしたたかさには感心するしかない。結局、幕府は例外を認めざるを得なかった。
5.岩永三五郎の石橋架橋と水防戦略
甲突川には幕末に肥後の石工岩永三五郎が築いたいわゆる五石橋が架かっていた(図2)。これは天保改革の総仕上げとして、天候に左右されず各方面の国産品を鹿児島港へ運ぶ物資流通の大動脈(産業道路)として建設されたものである。4連・5連の長大橋で、市民の誇りであった。しかし残念ながら1993年の豪雨災害で新上橋・武之橋の2橋が流失してしまった。他の石橋も水防上障害になるとして撤去されることが決定している。当然、文化財を守れとの反対運動が起きたが、既に玉江橋は撤去された。
 図2 甲突川五石橋
図2 甲突川五石橋
三五郎の水防戦略は次のようなものであった。①河道を矯正すると同時に、下流部の浚渫を行った(その時の残土を積み上げたのが薩英戦争で名高い天保山である)。②城下側の堤防に比べて対岸荒田側を意識的に1尺低くし、洪水時には溢水が田園地帯に氾濫するように企図した。民家には舟筏を用意させたという。肥沃な土壌を供給することも狙ったのかも知れない。③城下側には石組みの連続堤防を築き氾濫を防止した。④洪水が直進しやすい性質を知っていて、蛇行部の直ぐ下流に石橋を設置し、石橋への洪水流の直撃を避けるよう設計した。⑤上流水源地帯の保水力を維持するために、山の木を切ることを固く禁じた。いずれも川の性質を熟知した上での巧妙な対策である。ある程度の被害は甘受しながらも、大勢の人々の住む城下町と高価な石橋を守ろうとの、硬軟巧みに使い分けた災害との共存の思想がうかがえる。水害に対する備えを忘れ安易に地下室を作った現代人は、舟筏を用意していた祖先の発想に学ぶ必要があろう。
6.明治~昭和期の水害
災害は忘れた頃にやってくる。甲突川が氾濫するとは多くの市民は思っていなかったに違いない。近年中上流部に大規模団地を造成したために、山地の保水機能が低下して水害になったとの論調が盛んである。しかし、自然の状態が良好に保たれてきた明治~昭和期にも同規模の水害はしばしば発生していた(表1)。被災地をみると、いずれも旧河道と三五郎の予定していた遊水地が冠水している。水は地形学の優等生である。
当時の新聞によると、水害後何時までも水が引かないので棒を突き刺してみたら、水の深さは1尺ほどしかなかったという。つまり、ものすごい土砂が流れ込んで河床が急激に上昇したのである。しらす地帯を流れる川は、上流部での土砂生産が桁違いに多いから、水だけのことを考えた治水対策ではダメだということを意味する。天保山の故事も同じ事を示している。“平成山”が必要なのだろうか。
表1 主な甲突川水害
────────────────────────────────────────
発生年月日 日雨量(mm) 被害状況(新聞報道による)
────────────────────────────────────────
明治31.7. 5 206.6 西田町・鷹師馬場・薬師馬場・高麗町浸水
明治40.7. 6 200.9 市内大部分浸水,鷹師・薬師両町床上浸水
大正 6.6.16 305.7 西田・薬師・鷹師・草牟田町浸水,山之口通り浸水
大正 8.6.15 216.9 草牟田町・新照院浸水5尺,鷹師町床上浸水
昭和 3.6.21 255.0 西田橋被害,甲突川増水4尺、浸水家屋763戸
昭和11.7.23 233.8 浸水家屋1万戸,床上浸水300戸
昭和23.6.25 210.4 西田町・塩屋町・天保山町浸水
昭和24.6.28 238.3 市内中央部を除き一面泥水の街と化す
昭和27.6. 8 206.8 市内約1千戸床下浸水
昭和44.7. 5 76.0 甲突川氾濫
平成 1.7.28 257.5 甲突川氾濫
平成 5. 8.6 259.0 冠水市内424ha, 11,586戸浸水
────────────────────────────────────────
7.おわりに
以上略述したように、自然条件の厳しい南九州では、好むと好まざるとに関わらず自然災害とつき合わなければならなかった。むしろ災害を前提として社会全体が築かれてきたといってもよい。自然の理をよくわきまえ見事に対処してきたのである。写真1は1986年災害時の鹿児島市内武地区の被災状況であるが、典型的なしらす台地の地形を示している。台地があって急崖があり、その麓にはなだらかな坂がある。この坂の部分が終わって平地になったところ、左下端の木の生い繁った公園が西郷屋敷跡である。征韓論に破れて下野した西郷隆盛が住んでいたところという。上記の坂の部分こそ崩積土の堆積地形であり、崖崩れの土砂に襲われる恐れの強いところである。昔の人はそれを知っていて、この部分は竹薮のまま放置しておくか、菜園にしておいた。恐らく西郷屋敷も山際の閑静な住宅だったのだろう。このように祖先の知恵には現代に通じる数々の教訓が秘められている。それ故に災害文化というのであろう。なお、現行の鹿児島県宅地造成基準では崖肩を望んで仰角30゜以上は宅造が禁止されている。35゜までは公園や道路には使用してよい。1976年・1986年災害の被災家屋はすべてこの30゜ライン内に入っていた。戦後、人間のほうが自然の領域を侵して近づきすぎたのである。コンクリート法面に囲まれた異様な町にしてギリギリまで土地利用するのか、一歩自然に譲って緑豊かな町のままにしておくのか、選択の問題である。私見では、数10年に1回程度崩れることはあっても、緑に囲まれて住みたいと思う。鹿児島市では「がけ地近接等危険住宅移転事業」を行い、補助金を交付して安全な場所への移転を勧めている。
最後に、1993年鹿児島豪雨災害の経験でいえば、都会化し地縁社会が崩壊する中で、こうした災害文化の伝承が怠られ、教訓が生かされていないように思える。災害弱者の問題もあり、自主防災組織などを通じてもう一度地縁社会の復活を図る必要がある。一方、自然災害に慣れっこになってしまい、集中豪雨があっても、またかと軽く考えて避難しなかった事例も多く見られた。マイナスの災害文化もある。心したいものである。
 写真1 しらす台地の地形(鹿児島市武地区)
写真1 しらす台地の地形(鹿児島市武地区)
ページ先頭|災害科学雑文集もくじへ戻る
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:1997年8月19日
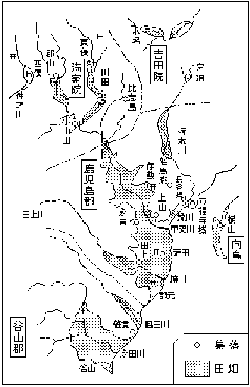 図1 南北朝時代の鹿児島
図1 南北朝時代の鹿児島 図2 甲突川五石橋
図2 甲突川五石橋 写真1 しらす台地の地形(鹿児島市武地区)
写真1 しらす台地の地形(鹿児島市武地区)